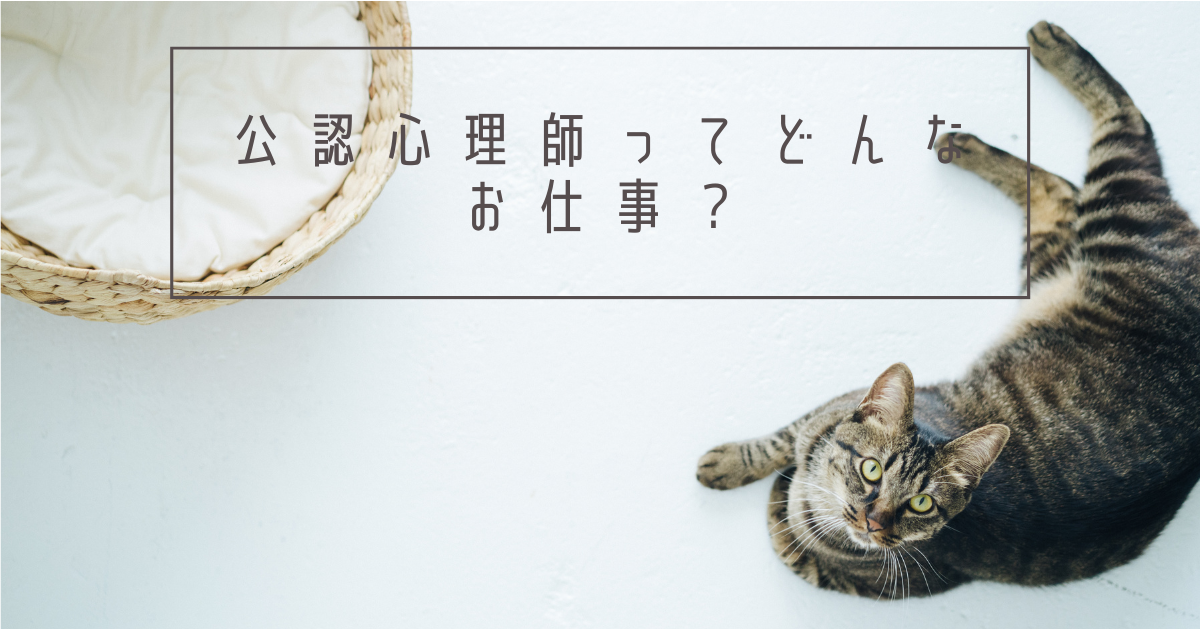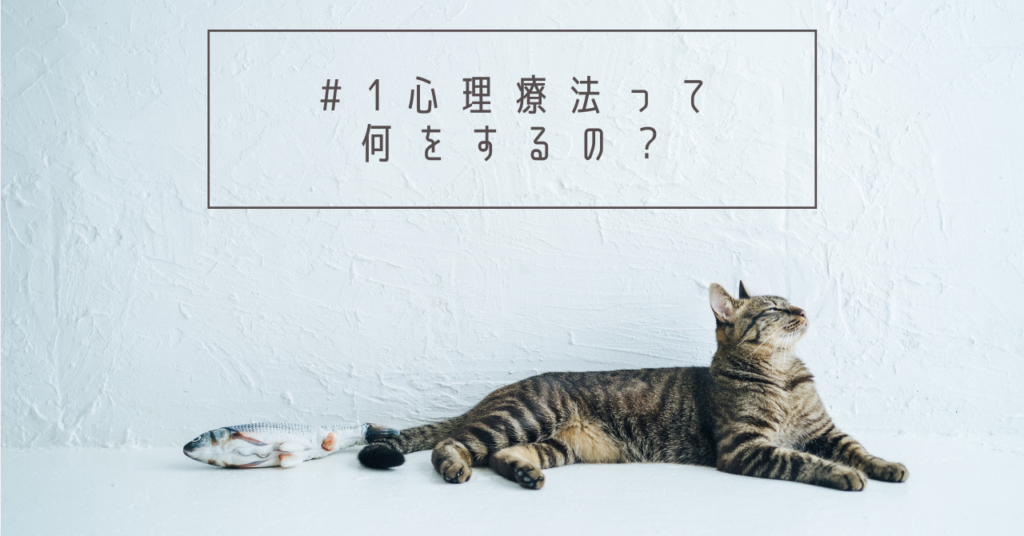皆さん、こんにちは。臨床心理士、公認心理師のNicoです。
Nicoの心理療法の庭へようこそ。

今日も一緒に心理学や心理療法について勉強しよう!
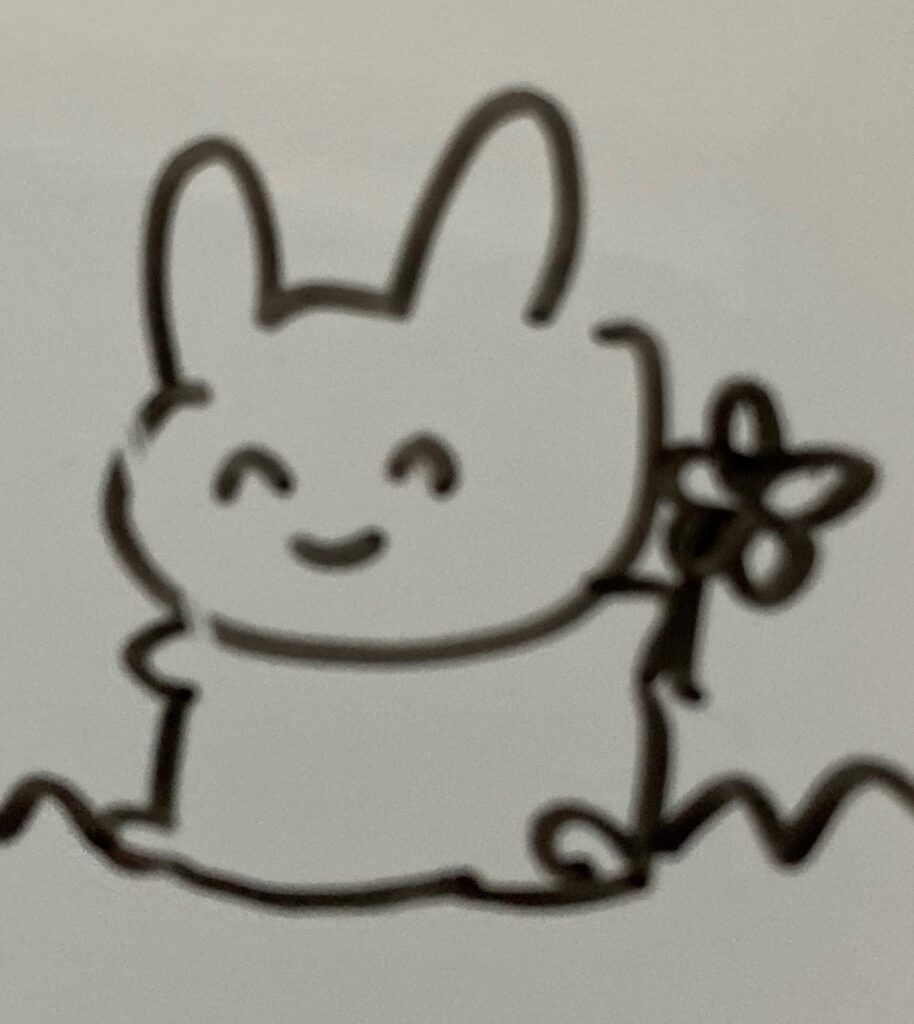
- 名前:Nico
- 国立大学、同大学院で臨床心理学を専攻、博士号取得
- 臨床心理士(臨床心理士の資格と現状 の記事)
- 公認心理師(公認心理師の資格と現状 の記事)
- 10年以上、教育機関、精神科クリニックなどで心理検査や心理療法(カウンセリング)といった臨床実践を行い、
- 定期的にスーパーバイザーから指導も受けている。
- 専門性・信頼性のある文献・情報をもとに、噛み砕いて発信します!
今回のテーマは、公認心理師の仕事と現状です。
臨床心理士の仕事と現状の記事でも触れたようにように、現在の日本では、「~心理士」や「~カウンセラー」「~セラピスト」といった名前のつく資格は、たくさんあります。
そのため、皆さんのなかには、
- 「公認心理師の資格って、これまでの心理の資格とどう違かよくわからない」
- 「相談するとすれば、どの資格をもっている人が良いかわからない」
- 「公認心理師の取得を考えているけれど、その過程や将来性について知りたい」
といった方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで今回は、私がもっている資格の一つである公認心理師について、
- 公認心理師の概要・取得ルート
- 公認心理師の業務・法的な位置づけ
- 現時点での公認心理師をめぐる課題
という観点から解説していきたいと思います。
公認心理師について、読者の皆さんにより具体的な知識・イメージをもっていただければ
- 「自分に合った心の専門家」を探しやすくなる
- ご自身の将来のキャリアプランを考える材料になる
- 社会により有益な心理職になり、かつ、自らも適正な評価や報酬を得るための方向性を考えるきっかけになる
と思います。

知るって大事だもんね

知っていれば、不安も小さくなるからね。
「知は力」だよ!
心理職初の国家資格 公認心理師へのなり方
公認心理師は、「国民の心の健康の保持増進に寄与すること」を目的として、2015年に制定された公認心理師法をもとに、2019年に誕生した日本の心理職で初の国家資格です(第1回資格試験は2018年実施)。
公認心理師の受験資格を得るには、複数のルート(計8つ)があります。たとえば
- 大学4年と大学院2年で指定科目を履修(実習含む)
- 大学4年で指定科目を履修し、その後2年以上の実務経験を積む
といった通常ルートの他、新しい資格であるため、5年間の経過措置として
「5年以上の実務経験+現任者講習の受講」(2022年実施済の第5回試験まで)
といったルートもあります。
資格試験は、マークシート形式で行われ、試験に合格後、公認心理師登録簿への登録申請をし、登録を受けることによって、公認心理師を名乗れるようになります。

公認心理士のお仕事ー従来の心理士との違い
業務内容の特徴 実務者・技術者としての側面の強調
公認心理師の業務は、以下のように定義されています。
公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
厚生労働省HPより引用(太字はNico)
業務内容に関しては、従来の心理職の業務から大幅に変更された部分は多くないと思われますが、公認心理師の業務には、臨床心理士のような「研究・調査」は含まれておらず、実務者・技術者としての側面がより強調されたと思われます。
その分、従来の業務がより細かく規定され、要支援者の関係者への援助や、心の健康に関する「教育・情報の提供」が明文化されたと言えるでしょう。

国家資格としての意義 法的な責任や保障の明確化
また、公認心理師は、医師や弁護士のような業務独占の資格ではなく、名称独占の資格です。
そのため、公認心理師の資格がなくても、従来の心理的援助業務自体は可能ですが、資格を取って初めて「公認心理師」「心理師」を名乗ることが許されます。
これは、つまり、国によって定められたカリキュラム(あるいは実務経験)と試験をクリアした心理職の専門家として線引きを行い、その法的な保障や責任の範囲を明確化することを意図していると考えられます。
法的な保障の例としては、
公認心理師が関与する業務が診療報酬算定の対象となり、徐々にその範囲が広がっていること(梨谷,2020;公認心理師協会,2022)
が挙げられます。
法的な責任については、次の「公認心理師をめぐる課題」で触れます。
そのため、これから心理職として公的機関や医療機関で勤務するには、公認心理師の資格取得が必須になるかもしれません。

保険診療の対象になる心理的援助が広がると良いね!

そうだね。医療費の問題もあるから「一気に」とはいかないけれど、
患者さんの負担軽減と、公認心理師の雇用安定の両方に繋がるからね。
公認心理師をめぐる課題 職務上の立場とカリキュラム
公認心理師の制度設計には、
- 臨床心理士関連団体
- 行政
- 日本医師会
- 基礎心理学の関連団体
など、さまざまな団体が深く関わったため、その立場や養成カリキュラムが、従来目指していたものとは異なるものになってしまったという批判もあります(河村,2018;下山・伊藤,2021;山中,2019;2022など)。

公認心理師の立場ー主治医との関係
その一例として、主治医との関係があります。
公認心理師法第 42 条第 2 項では、公認心理師が業務を行う際、
心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない
と医師との関係性が定められています。
つまり、
心理的な支援に関する主治医がいる場合には、合理的な理由がある場合以外、その主治医の指示を受けなければならない
ということです。
その目的とするところは、
公認心理師が、主治医の治療方針とは異なる支援行為を行うことによって、要支援者に効果的な改善が図られないことを防ぐため
とされています。

もちろん、これまでの臨床心理士の活動においても、医師や支援関係者との連携は行われてきました。
ただ、当初から臨床心理士は、《医師と対等にモノが言える臨床心理「師」》(山中,2019)という立場を目標としていました(➡「臨床心理士」の資格と現状も参照)
それが公認心理師法によって、
公認心理師と医師のあいだで、心理的な支援に関する見解や立場が異なる場合に優先される支援方針が法的に方向づけられた
とも言えるかもしれません。
そのため、公認心理師においては、より一層、支援方針についての説明責任が求められるようになったと言えるでしょう。

専門職なんだから、説明責任は当然なんじゃないの?

その通りだね!
ただ、ここがちょっと難しい所でもあるんだ。
個別のケースにおいては、誰の目から見て、あるいはどんな価値観や文脈から見て『合理的』と判断するのかが重要
となります。
心理的援助は本来、患者なりの『理』(判断のもととなる理屈、価値体系)に耳を傾けることを通して、心理的成長や回復を支えるものと考えられます。
そして、
主治医が非常に柔軟で、患者の立場やその心理的援助にも理解を示される場合
➡患者、医師、心理師の三者間で『理』が近いので、あまり問題は生じません。
一方で、
患者と主治医のあいだで『理』が異なり、かみ合わない場合
➡そこに関わる心理師の援助方針や言動は、法律上、主治医の『理』や指示による影響や制約を免れられない。
➡患者の『理』に耳を傾けるという心理師の姿勢や態度に微妙な、しかし大きな変化が生じる
結果として、心理師の援助行為が難しい立場に置かれかねないと言われるわけです。

患者さんと主治医のあいだで動きやすくいるための工夫が必要そうだね。

そうだね。そのためには、心理士が自分の援助方針を患者さんにも主治医にも
わかりやすく説明できるようにしておく必要がありそうだね。
以上のことから公認心理師には、医師と患者双方の異なる『理』が接点をもてるように、より高い水準で、自らの援助方針を説明できるようになることが求められると考えられます。
ただこれは、いわゆる論理的思考に基づいて話す人と、感情に基づいて話す人が対立している場合に、双方を取り結ぶのが難しいように、非常に難しいところです。
養成カリキュラムについての課題・懸念

公認心理師の養成カリキュラムについては、学ぶ内容が、
- 臨床心理学
- 基礎心理学(知覚や認知、学習・言語、脳・神経、社会・集団・家族心理など)
- 医学的知識(精神疾患のほか、心身機能や身体構造なども含む)
- 関連する法令・制度などの細かな行政的知識
というように非常に幅広く、学部カリキュラムへの「詰め込み」という批判もあります(下山・伊藤,2021)。
また、大学院では、実習カリキュラムをこなすことと、資格試験のための勉強時間の確保で一杯一杯になり、修士論文を執筆する時間がまともに取れないのではないかという懸念もあると聞きます。
それでは、大学院の本来の目的である、専門的な学びを深め、研究の基礎的な能力を身に着けるということが難しくなり、本末転倒ということになりかねません。
現時点では、制度ができてまだそれほど時間が経っていない揺籃期・移行期ということもあり、大学・大学院における養成カリキュラムや、職能団体などをめぐる課題も多いですが、今後の発展に向けた努力が行われているところです。
まとめ 公認心理師の資格と現状
ここまで、公認心理師の目的や業務、社会的な現状や立ち位置、今後の課題について解説してきました。まとめると、
- 公認心理師は、日本初の心理職の国家資格で、実務者・技術者としての側面がより強調されている。
- 従来の心理職の実績をもとに、法的な保障や責任の範囲を明確化するものと考えられる。
- 公認心理師が関与する業務が保険診療の対象となり、その範囲は徐々に拡大している。
- 心理的支援の方針については、主治医の指示を受けなければならない。
- そのため、より一層の説明責任が求められると考えられる。
- まだ歴史は浅く、その立場やカリキュラムなどに課題はあるものの、今後、心理職として公的機関や医療機関に勤めるには、必須の資格になるかもしれない。
となります。
公認心理師の資格や現状について、より具体的なイメージをもっていただくことができれば、
- 自分に合った心理的援助・心の専門家を探しやすくなる
- ご自身の将来のキャリアプランを考える材料になる
- 社会により有益な心理職になり、なおかつ、自らも適正な評価や報酬を得るための方向性を考えるきっかけになる
と思います。この記事がそのお役に立てば幸いです。

心理職に限らず、精神科医療なども含めて、日本の心の健康をめぐる状況には課題が沢山あります。
そうした課題や現状について発信し、皆さんに伝えていくこと自体、専門家としての役割でもありますし、問題解決に繋がっていくと思います。

このブログは、心理学や心理療法(カウンセリング)についての情報を発信することで、読者の皆さんが、心理療法をもっと身近で、よりアクセスしやすいものと感じられるようになることを目指しています。

それでは今日も、ありがとうございました!
- 河村建夫(2018)臨床心理士への新たな期待.臨床心理士報,29(2),3‐7.
- 厚生労働省 公認心理師 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html 2022年9月8日閲覧.
- 公認心理師協会 保健医療分野委員会(2022)【解説】診療報酬に収載されている公認心理師が関与する業務.medicalfees_cpp.pdf (jacpp.or.jp) 2022年9月17日閲覧.
- 厚生労働省HP 「公認心理師法第 42 条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について」.Microsoft Word – 【通知】医師の指示180131 (mhlw.go.jp) 2022年9月8日閲覧.
- 梨谷竜也(2020)令和2年度診療報酬改定について.日本臨床心理士会雑誌,29(1),46‐47.
- 下山晴彦・伊藤絵美(2021)“仲間割れ”を巡る長い前置きー(特集 伊藤絵美先生との対話).臨床心理マガジンiNEXT,19(1).19-1.“仲間割れ”を巡る長い前置き|臨床心理マガジンiNEXT|note 2022年9月8日閲覧.
- 山中康裕(2019)一貫して考えていたこと.臨床心理士報,30(2),1‐3.
- 山中康裕(2022)若き臨床心理士の諸君へのエール.臨床心理士報,33(1),1‐3.
この次に読んでもらいたい記事