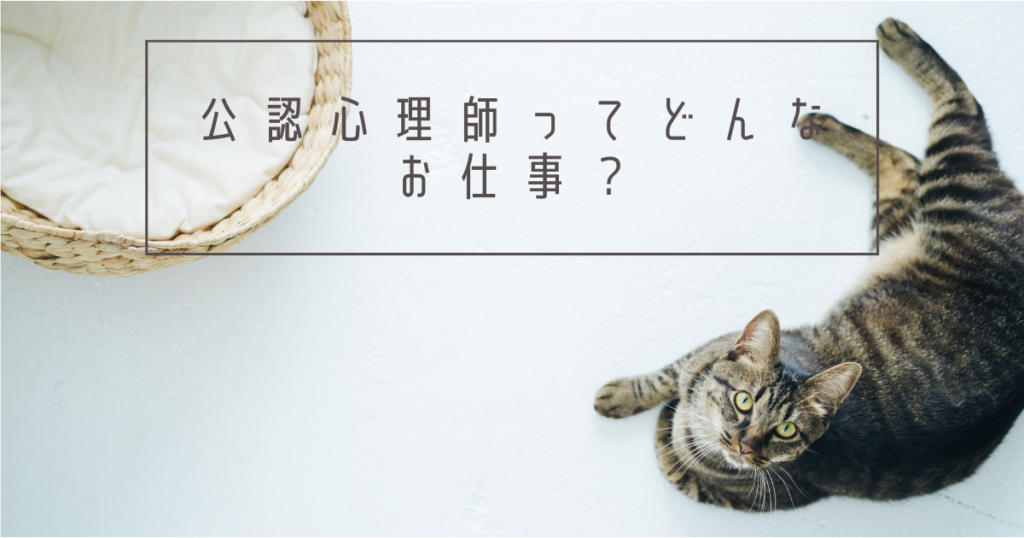皆さん、こんにちは。臨床心理士、公認心理師のNicoです。
Nicoの心理療法の庭へようこそ。

今日も一緒に心理学や心理療法について勉強しよう!
今回のテーマは、「臨床心理士」の資格と現状です。
臨床心理士は、内閣府認可の公益財団法人「日本臨床心理士資格認定協会」による認定資格(特許庁商標登録番号:第4808560号)で、臨床心理士第1号は1988年に誕生しました。
現在の日本では、「~心理士」や「~カウンセラー」「~セラピスト」といった名前のつく民間資格がたくさんあります。しかし、そのなかには、数日~数か月の講習や模擬面接で資格や受験資格が得られてしまうものもあります。
もちろん、個人の関心や趣味として学び、そうした資格を取得することは、意味がありますし、それが周囲の人との関わりの役に立つこともあるでしょう。
一方で、他者の心の健康に携わる仕事をしたいと考えるならば、より濃密で長期にわたる学術的、実践的訓練カリキュラムを経た資格を取得しておくことが、最低ラインとして求められるはずです。
例として、身体の健康に携わる医師は、大学医学部で6年間学び、ようやく国家試験を受けられます。さらにそのあと、2年以上の臨床研修を受けることで、医師として診療を行えるようになります。
もし仮に、医師がごく短期間の座学や見学で取得され、診療を行っているとしたら、その治療を受けたいと考えるでしょうか?

とは言え、「臨床心理士」がどのような資格なのか、どのような訓練を最低限受けているかについては、あまり知られていないと思われます。
そこでこの記事では、臨床心理士の資格について、次の5つにわけて解説します。
- 臨床心理士の理念と概要
- 臨床心理士の仕事4つ
- 主な取得ルート、訓練課程
- 臨床心理士取得後の自己研鑽(訓練・教育)
- 臨床心理士として働くうえでの課題

それでは、行ってみましょう!
臨床心理士ってどんな資格?ー30年以上の実績
臨床心理士の創設に深く携わった精神科医の山中(2019;2022)によれば、臨床心理士は、
「《医師と対等にモノが言える臨床心理「師」》つまり、医師が《からだ》の護り手の総責任者であるとするなら、臨床心理「師」は、《こころ》の守り手の総責任者たるべき」
山中康裕(2019;2022)
という思想のもと、当初から、これをそのまま国家資格に移行することを目標として創られました。
しかし、医療費抑制や、医師との関係性、心理学関連団体との関係などの問題があり、臨床心理士の国家資格への移行は、実現していません(河村,2018;山中,2019;2022)。
また、心理的援助に関する業務を独占業務として認める法律もまだありません。
そのため、さまざまな民間資格が乱立してしまい、利用者にとって「どの資格をもった人が心の健康に関する相談に適しているかよくわからない」状況が続いています。
それでも、1995年に始まった旧・文部省(現・文部科学省)所管のスクールカウンセラー派遣事業を通じて、臨床心理士の存在は広く知られるようになっていきました。
臨床心理士の活動領域は、
- 教育
- 保健医療
- 福祉
- 司法・犯罪
- 産業・労働
- 私設心理臨床(開業)
と多岐にわたります。

2023年現在、臨床心理士は、日本の心理職を代表する専門職として30年以上の実績があるんだ。たくさんの人が頑張ってきたんだね!

臨床心理士のお仕事4つ
このような臨床心理士の専門的業務は、4つあります。
(公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会HPと心理臨床大事典(2004)を参考に作成)
1.臨床心理査定
- 心理検査や、来談者(クライエント)の話をもとに、その人の「人となり」、心理的特徴のあり方について仮説的な理解を立て、クライエントや関係者に伝える仕事です。
医学と異なり、「診断diagnosis」ではなく、「見立て・査定assessment」と言います。
2.臨床心理面接
- 見立てをもとに、クライエントが自身の課題と向き合い、その人なりの答え(心理的により満足、納得できる状態)を見つけるプロセスを援助します。
これが「カウンセリング」「心理療法(医師が行う場合は、精神療法といいます)」「サイコセラピー(セラピー)」などと呼ばれる仕事です。

3.臨床心理的地域援助
臨床心理学の知見を用いて、地域社会の心理的健康の維持・増進に貢献する仕事です。
たとえば、
- 他の専門家に対する臨床心理学的側面からの助言(コンサルテーション)
- より効果的な援助のための学校、職場、地域社会などへの働きかけ(コーディネーション)
- 学校や職場などで行われる、ソーシャルスキル講習やメンタルヘルス講習といった予防活動
- 災害時や事件発生後の危機介入
- 心の問題について臨床心理学に基づいた適切な情報を提供する活動
などがあります。
4.1~3についての研究・調査
上に述べた仕事を通じて臨床心理士個人が得た成長は、当然、目の前のクライエントに還元されます。
しかし、それだけにとどまらず、
- 研究・調査を通じて、臨床心理士個人の成長を専門的知見にまで高めること
が求められています。
そうして生まれた知見を、他のクライエントや社会に還元してゆくことまでが、臨床心理士の専門的業務とされています。

つまり、臨床心理士の業務は、研究・調査まで含むことで、次のような好循環を目指しているんだ。ここが臨床心理士の大きな特徴のひとつだよ。
- 専門的知見・訓練に基づく心理臨床実践活動(クライエントへの援助)
- ➡目の前のクライエントの心理的成長・回復、かつ、臨床心理士の成長・経験の蓄積
- ➡臨床心理士の経験を専門的知見に高めるための調査研究
- ➡より高度な専門的知見をエビデンスとした心理臨床実践活動(再びクライエントへの援助)

実践と研究の両方があって好循環が生まれるんだね!

臨床心理士になる主なルート、訓練課程
臨床心理士の資格試験を受けるための主なルートとして、まず、「公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会」によって認可された臨床心理士養成に関する指定大学院で2年間の教育・訓練(修士号取得)を受ける必要があります。

受験資格を得るルートには、他にも「専門職大学院での訓練」や「医師免許の取得と実務経験」といったものがありますが、私の経験の範囲外ですので、ここでは割愛させていただきます。
その教育・訓練は、講義だけに留まりません。たとえば、
- 大学院附属の相談機関において、援助を必要としている人と実際に臨床心理査定や臨床心理面接を行う。
- その内容について上級の専門家からの指導を受ける(スーパーヴィジョン。実費であることが多い)。
- 上級の専門家や訓練生と共に議論し、学ぶ機会をもつ(ケース・カンファレンス)。
- 病院や学校などの外部実習機関での援助業務に携わる(無償もしくは有償)。
といった、実践的訓練を積みます。
さらに、臨床心理士に求められる研究・調査能力を身に着けるために、修士論文の執筆、提出も求められます。
こうして2年間の訓練課程を修了すると、臨床心理士の受験資格が得られます。
上記の2年間の教育・訓練課程(修士課程、博士前期課程)を終えた翌年度以降、
- マークシート形式の試験と小論文、面接試験を通過し、
- 臨床心理士としての登録手続きを済ませる
ことで、臨床心理士を名乗ることができるようになります。

臨床心理士になってからの自己研鑽3つ
臨床心理士には、その資質向上のための生涯学習や自己研鑽が求められます。
つまり、資格取得後も、専門性をより高めるための行動を続ける必要があります。
以下に、私の経験をもとに、臨床心理士としての自己研鑽を3点に分けて述べます。
1.研修会やスーパーヴィジョンによる自己研鑽
臨床心理士は、上に述べた理由から、5年更新制の資格となっています。
更新の要件は、次のような研鑽を積み、知識をアップデートして必要なポイントを取得することです。
- 研修会や学会への参加・発表
- 論文や著書の執筆
- 継続的なスーパーヴィジョンを受ける
そのほか、教育分析(心理士自身が、上級の専門家による治療を体験し、自分の心に向き合う面接)を受けることも大切とされています。
そのため、臨床心理士は、資格取得後も、研鑽の費用がかかります。

2.博士課程に進学して体験知を得る
また、2年間の修士課程(博士前期課程)を終えた後も、博士課程(博士後期課程)に進学する人もいます。
博士課程では、外部機関でも働きながら、大学院附属の相談機関において、心理臨床家(セラピスト、カウンセラー)としての訓練を重ねます。
博士課程は最短でも3年ありますので、修士課程と合わせると、短くて5年の訓練を重ねることになります。

ええっ!そんなに長いの!?

実はそうなんだ。深い悩みを抱えるクライエントが、本当に納得のいく答えを見つけて、大きく成長するプロセスにお付き合いするには、数年を要するのは決して珍しいことではないからね。

そのため、
- 博士課程への進学には、「できる限り最後まで、クライエントのプロセスにお付き合いし、深い悩みから大きく成長・変化してゆく人の心の動きを体験的に学ぶ」という側面がある
- この心のプロセスの全体像を1つでも多く、体験として知っているかどうかは、臨床心理士としての力量を大きく左右する
- 博士課程を経た臨床心理士は、長期にわたる心理療法の実施経験通して、悩みを抱える人の心の動きについての体験知をより多く獲得している可能性が高い
と考えられます。

特に大学院附属の相談機関は、営利ではなく教育・訓練を目的とするから、クライエント、セラピスト双方がじっくりと心のプロセスに取り組むための理想的な環境が整えられていることが多いんだよ。

博士課程に進んだ人は、より濃い訓練を受けてるってことだね。
3.博士論文を執筆し、体験知を専門的知見に高める
さらに、自身の臨床経験や関心を専門的知見に高める自己研鑽として、博士号を取得(博士課程を修了)することが挙げられます。
ただ、その前提として、複数の論文を査読付き学術誌(複数の専門家による審査を経て出版される)に掲載する必要があります。

実際に求められる論文の数などは、
博士論文を提出する大学院や研究室によって多少異なるよ。
それをクリアしたのちに、以下のプロセスを経て、博士号の授与が決まります。
- 博士論文を執筆し、
- 異なる分野の教授も含めた教授会で審査を受け、
- 高い専門性や、異なる分野からも見た妥当性と、論文のオリジナリティが認められる

大変そう!ぴーーっ!!💦

これには、かなりの労力と時間が必要です。
そのため、博士号を取るために、
- 博士課程に4年以上在籍する人
- 単位を修得して博士課程を退学した後も、数年かけて論文を執筆する人
- 修士課程を終えた後、すぐに博士課程に進学するのではなく、社会人として暫く経験を積み、ある程度論文を書いた段階で、博士課程に入り直す人
など、さまざまです。
もちろん、臨床心理士として活動するうえで、博士号の取得は必須ではありません。
その一方で、博士号を取得することは、自他の心について深く体験し、学び、それを言葉にして説明する作業であり、専門家としての資質向上に大きく寄与すると考えられます。

博士号は高い専門性の証なんだね!

臨床心理士として働くうえでの課題ー社会的立場と経済状況
臨床心理士として働くうえでの課題は何といっても、
- 資格取得や維持にかかる要件や費用が厳しい
- その割に、就業・雇用が不安定で、報酬が低くなりがち
- 十分な社会保障を受けにくいことも多い
点にあると思われます。
その「背景には、臨床心理士が国家資格ではないことの影響も大きい」(坂本,2019)とも言われています。
たとえば、臨床心理士の仕事は、医療保険制度(診療報酬への算定)が適用されるものが少ないため、医療機関が臨床心理士を雇っても、直接的な収益はほとんど出ません。
そのため、「看護師や作業療法士、精神保健福祉士といった国家資格をもつコメディカルスタッフとは同等に扱われにくい状況が続いた」(坂本,2019)とされます。
つまり、臨床心理士は、資格取得・維持のために必要な経費や労力に対して、適正な評価や報酬が得られにくいという状況が続いていると考えられます。

具体的なデータを見てみましょう。
日本臨床心理士会による臨床心理士の動向調査の報告書(2012,2016,2020:いずれも約1万人の臨床心理士が回答)によれば、その就業形態は
| 2012年 | 2016年 | 2020年 | |
| 常勤のみ | 33.5% | 33.8% | 34.9% |
| 常勤+非常勤 | 14.2% | 13.8% | 13.1% |
| 非常勤のみ | 45.0% | 44.7% | 46.1% |
*現在は勤務していない(退職含む)、無回答を除いているため、合計は100%にならない。
と、4割以上が「非常勤のみ」という状態が続いています。
実際、臨床心理士の求人は、非常勤や有期雇用といった雇用形態のものも多く、複数の機関での非常勤職をかけもちして生計を立てている人もたくさんいます。
次に、1人の臨床心理士が勤務する機関の数を見てみましょう。
| 2012年 | 2016年 | 2020年 | |
| 1機関 | 35.9% | 48.4% | 52.7% |
| 2機関 | 16.6% | 25.9% | 25.2% |
| 3機関 | 10.5% | 12.0% | 11.0% |
| 4機関 | 7.1% | 4.2% | 3.6% |
| 5機関 | 4.8% | 1.4% | 1.1% |
| 6機関以上 | 11.3% | 0.5% | 0.3% |
*無回答を除いているため、合計は100%にならない。
徐々に掛け持ちの人は減りつつあるのかもしれませんが、それでも約半数の人が掛け持ちをしている状況です。

さらに、見込み年収は、200万円台~400万円台の階級で回答者の約半数を占める状態が続いています。
2012年の報告書では、臨床心理士の年収の中央値は300万円台で、日本の年収の中央値と近いと考えられます。大学院修士課程修了が前提になっている職業の年収としては、低いと言わざるを得ないでしょう。
| 2012年 | 2016年 | 2020年 | |
| 100万未満 | 5.0% | 5.7% | 6.0% |
| 100万円台 | 9.4% | 8.8% | 9.7% |
| 200万円台 | 16.4% | 16.5% | 16.6% |
| 300万円台 | 20.0% | 19.0% | 19.0% |
| 400万円台 | 14.9% | 15.5% | 14.6% |
| 500万円台 | 8.7% | 9.3% | 10.0% |
| 600万円台 | 5.4% | 5.8% | 6.2% |
| 700万円台 | 4.4% | 4.1% | 3.8% |
| 800万円台 | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| 900万円台 | 1.9% | 1.8% | 1.8% |
| 1000万以上 | 3.4% | 3.3% | 3.6% |
| 無回答 | 7.9% | 7.6% | 6.1% |
*2020年度は、1000万以上の階級がより細分化されているが、ここでは一括して記載した。
なお、これらの動向調査報告書では、職域と年収の関連は述べられていないため、幾分推測になってしまいますが、ある程度以上に高い収入を得られているのは、
- 大学で教員のポストにつけた方
- 医師としても活動されている方
- その他、公務員などの常勤職で長年勤められ、管理職についている方
などではないかと考えられます。
これらの場合も、臨床心理士の資格取得に加えて、多くの訓練・修行を経たのちに、ようやく安定を得るということが多いのではないかと思われます。
一方で、「『スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化に向けた調査研究』の報告」(高田・石川,2022)など、臨床心理士の雇用状況の改善に繋がる努力も行われています。

まとめ 臨床心理士の資格と現状
ここまで、臨床心理士の目標や業務、社会的な現状や立ち位置、今後の課題について解説してきました。まとめると、
- 臨床心理士は、先人たちによる30年以上の実績がある認定資格。
- 最低2年以上、大学院や学内外の実習機関での教育・実地訓練を受ている。
- 5年更新制の資格で、取得後もスーパーヴィジョンやさまざまな研鑽を積む必要がある。
- 博士課程に進学し、より長期の濃密な訓練を受ける人もいる。
- 博士号を取得して、自身の専門性や資質の向上と、専門的知見の蓄積に努める人もいる。
- ただ、資格取得・維持に必要な経費や労力に対して、就業・雇用状況は必ずしも安定しているとは言えない。
- 一方で、今後の就業・雇用状況の改善に向けた努力も行われている。
臨床心理士について、より具体的なイメージをもっていただくことができれば、
- 「自分に合った心理的援助・心の専門家」を探しやすくなる
- ご自身の将来のキャリアプランを考える材料になる
- 社会により有益な心理職になり、なおかつ、自らも適正な評価や報酬を得るための方向性を考えるきっかけになる
と思います。この記事がそのお役に立てば幸いです。

心理職に限らず、精神科医療なども含めて、日本の心の健康をめぐる状況には課題が沢山あります。
そうした課題や現状について発信し、皆さんに伝えていくこと自体、専門家としての役割でもありますし、問題解決に繋がっていくと思います。

このブログは、心理学や心理療法(カウンセリング)についての情報を発信することで、読者の皆さんが、心理療法をもっと身近で、よりアクセスしやすいものと感じられるようになることを目指しています。

それでは今日も、ありがとうございました!
- 河村建夫(2018)臨床心理士への新たな期待.臨床心理士報,29(2),3‐7.
- 日本臨床心理士会(2012)第6回「臨床心理士の動向調査」報告書.
- 日本臨床心理士会(2016)第7回「臨床心理士の動向調査」報告書.
- 日本臨床心理士会(2020)第8回「臨床心理士の動向調査」報告書.
- 日本臨床心理士会(2022)「スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化に向けた調査研究」の報告.日本臨床心理士会雑誌,31(1),32‐33.
- 臨床心理士資格認定協会HP 臨床心理士の専門業務. 臨床心理士の専門業務 | 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会 (fjcbcp.or.jp) 2022年9月8日閲覧.
- 坂本憲治(2019)心理専門職の求人情報の特徴と問題―2016年後半における臨床心理士の状況から―.福岡大学研究部論集B:社会科学編,11,23‐32.
- 氏原 寛・亀口憲治・成田善弘・東山紘久・山中康裕(共編)(2004)心理臨床大事典[改訂版].培風館.
- 山中康裕(2019)一貫して考えていたこと.臨床心理士報,30(2),1‐3.
- 山中康裕(2022)若き臨床心理士の諸君へのエール.臨床心理士報,33(1),1‐3.
この次に読んでもらいたい記事