
皆さん、こんにちは。臨床心理士、公認心理師のNicoです。
Nicoの心理療法の庭へようこそ。

今日も一緒に心理学や心理療法について勉強しよう!
今日のテーマは、【一体何のため?】心理療法の頻度が毎週or隔週に1回であることが多い理由です。
一般的に、心理療法は、1,2週間に1回、曜日と時間を固定して、定期的・集中的な設定で始めることが多いです(たとえば、毎週火曜日の12時からという具合)。
その際、次のような質問をいただくことがあります。
- 心理療法は毎週受けないとダメですか?相談したいときだけでも良いですか?
- 本当に毎週or隔週に1回の方が良いならば、その理由も知って納得したい。

結論から言えば、
- 時間や経済的事情の範囲内で、できるだけ毎週or隔週に1回の方が効果が高い。
- 集中的にした方が、自分の心身に目を向け、体験を丁寧に味わう習慣を作りやすいから。
となります。
ただ、こうした設定の問題は、専門的には「治療構造論」といって、それ自体非常に大きなテーマです。

そのため、ここでは、私の経験をもとに、皆さんが「心理療法を利用するかどうか」を判断するうえで役に立つことに絞ってお伝えします。
- 自分の心は後回しになりがち。
- だからこそ、定期的・集中的な心理療法で自分の心の優先順位をあげる方が良い。
- 定期的・集中的にするからこそ、自分の心を丁寧に見ることができる。
集中的な心理療法は、丁寧に生きる習慣作りをねらう
まず、心理療法を定期的・集中的に行う目的・ねらいは、
- クライエントが自分の心や体に目を向け、その体験を味わい、生きる習慣を作ること
にあります。
そのために、毎週や隔週に1回の時間を確保し、
- 心理的課題の優先順位を上げること
- 問題を細分化して詳しく検討すること
を勧めます。
なぜ、心や体に目を向ける習慣を作る必要があるのか。
それは、心理的な問題が次のようにして発生し、維持されていると考えられるからです。
- 私たち現代人は、日々忙しく、心や体が感じていることに目を向け、じっくり味わい、考える時間や習慣がもちにくい。
- そのため、「心や体が実際に感じていること」を抑え込み、無視する、あるいは、そうせざるを得ないことが多い。
- それが積み重なった結果、さまざまな悩みや心身の不調が生じる。
- しかし、悩みの背景にある心の習慣や癖は、自分ひとりでは捕まえにくく、解決の糸口が見えづらい。

たとえば、私たちは普段、
- 「やらなければならないこと」ーいろいろな仕事や家事、勉強、課題。
- 「周囲の人から期待されていること」ー家族や友人、学校や職場の人間関係
- 「こうあるべき、~すべき」ー社会通念や一般常識
といったことに追われています。
そのため、自分の心や体が感じていることは、ついつい後回しになりがちです。
たとえば、
- 「実際は私は何を感じているのか」
- 「私は本当はどうしたいのか、どうありたいのか」
- 「私は何に心地良さを感じるのか」
そうして溜まりに溜まったものが、心身の不調や悩みとなって現れてくると考えられます。
- 仕事のことを考えると心臓がどきどきする。
- やらないといけないことがあるのに、気分が重く、身体が動かない。
- なぜかあの人といるとイライラしてしまう、など。

もちろん、社会のなかで生きていくうえで、「やらなければならないこと」や「周囲の期待」に応えることは大切です。
ただ、自分の心や体からのメッセージを蔑ろにすることが習慣や癖となると、さまざまな問題が生じて、心や体が悲鳴をあげることになります。
これは見方を変えると、心身の不調や悩みは、「もっと自分の心に目を向けなさい」「心の癖や習慣を見直しなさい」と伝えてきているとも言えるでしょう。
つまり、「周囲に適応するためにかつては必要で有効だった癖や習慣」を新しく組み直すことが必要な時期にきていると考えられます。
集中的に時間を確保することで、心理的課題の優先順位を上げる。
しかし、長い時間をかけて作り上げられた心の習慣や癖を変えるのは、そう簡単ではありません。
そこで心理療法では、「1,2週間に1回、〇曜日の△時から▲時までは、自分の心について考える時間」というように、集中的に時間を確保することをお勧めします。
それによって、それまで後回しにしてしまっていた「自分の心や体のこと」の優先順位を上げることができます。

でも、1,2週間に1回だと、変化も少ないし、話すことがないんじゃない?

実際、そう言われる方も結構いるよ。

しかし、実のところ、
話すことがないというよりも、今までの習慣上、大切だと思って目を向けていなかった
というのが、より正確でしょう。
実際、1週間は24時間×7日=168時間、2週間は336時間もあります。
そのあいだには誰もが、いろいろな事柄を感じ、考え、行っているはずです。
集中的な心理療法により、そうした自分について語る時間を増やすということは、
- 実は自分が本当に好きなこと
- 自分の心が訴えていること
- 自分にとって譲れないもの
に触れ、自分を違った角度から見直すということに繋がります。

「大事だと思うから話す」のではなく、「語るから大事だと分かってくる」ことも多いですよ。
セラピスト(カウンセラー)の仕事は、クライエントの語りを聴き、問いを発し、ときにツッコミを入れ、感情や感覚を味わう時間を共にする他者の役割を担うことです。
そのようにして、クライエント自身は大切と思っていなかったことを取り上げ、その感じ方やあり方に変化を呼び込むのが心理療法です。
そこで味わう体験は、心地良いものばかりではないかもしれません。
- 「こんなはずじゃなかった」
- 「どうして自分がこんな目に遭わないといけないのか」
と悔しがったり、腹を立てたり、悲しんだりするかもしれません。
しかし、心理療法は、クライエントがそれも含めて自分の心と体を大切にすることで、本来の自分、自然な自分へと近づくお手伝いをします。

問題を細分化し、見落としていた体験を詳しく検討する。
また、心理療法によって、日々の生活を1,2週間という単位で細かく区切ることには、次のような効果もあります。
- 体験したことを鮮明に思い出せるうちに扱うことができる。
- それらの体験を詳しく検討することができる。
心の癖や習慣を変えることに限らず、難しい問題に対する鉄則は、「困難は分割せよ」です。
つまり、
- 問題を細かく分けて、取り扱える大きさにする
- 問題を見る目の解像度を上げる
です。

スモールステップってことだね。

面接の間が1か月もあると、さまざまな出来事が起こります。しかし、それをすべて鮮明に覚えているという人は少ないと思われます。1か月経っても思い出せるのは、
- よほど強く印象に残ったこと
- 今までの習慣上、意識が大事と思ったこと
くらいではないでしょうか。
もちろん、どちらもそれ自体が、「いつもと違うこと」や「何らかの変化」であるかもしれません。
それらは、心に大きな変化をもたらします。また、心理療法は、そうした体験が生じることを待つという側面もあります。
しかし、「いつもと違うこと」「何らかの変化」というのは、ただ待っているだけでなく、1,2週間の間でも、日々の生活を丁寧に見てみると、意外なほどに沢山あるものです。

セラピストは、そうした体験にも焦点を当てることで、
新しい心の習慣の基礎作りのお手伝いをします。
この基礎がしっかりすればするほど、クライエントは、小さな出来事も大きな変化のきっかけとして掴めるようになり、問題解決の糸口を見つけやすくなります。
そのため、心理療法のプロセスが進んで、意識の習慣にかなりの変化が定着したあとであれば、面接の頻度を下げても大丈夫かもしれません。
ただ、少なくとも初めのうちは、1,2週間に1回程度の頻度で行う方が、意識の習慣やあり方を変えてゆく上で有効だと思います。

まとめ 定期的・集中的な心理療法で新しい習慣を作る
今回は、心理療法の頻度が毎週or隔週に1回であることが多い理由について、以下の内容をお伝えしました。
- 現代人は「心や体が実際に感じていること」を抑え込み、無視せざるを得ないことが多い。
- 多くの悩みや心理的不調は、そうした心の癖を見つめ直す必要性を訴えている。
- そのため、時間や経済的事情の範囲内で集中的に時間を確保し、心の優先度をあげて、丁寧に検討することが有効。
- 少なくとも最初の方は集中的にする方が、新しい心の習慣の基礎をしっかりと作りやすい。
以上、参考になれば嬉しいです。

このブログは、心理学や心理療法(カウンセリング)についての情報を発信することで、読者の皆さんが、心理療法をもっと身近で、よりアクセスしやすいものと感じられるようになることを目指しています。

それでは今日も、ありがとうございました!
Nico
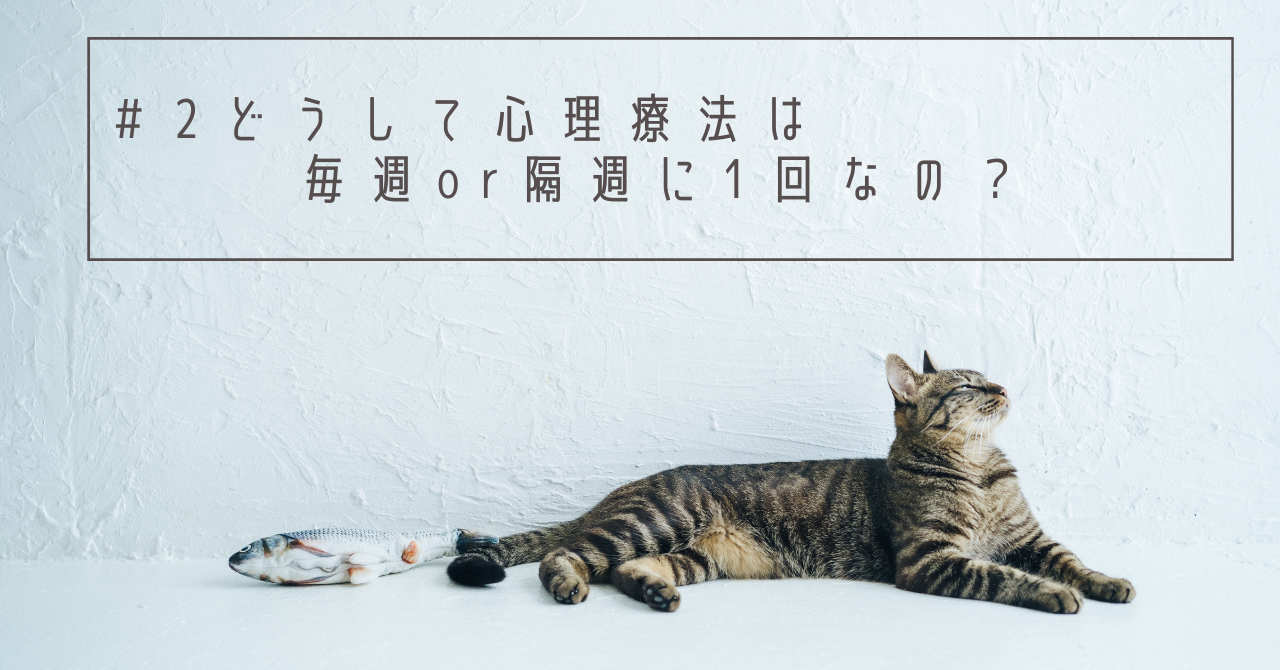


コメント