
皆さん、こんにちは。臨床心理士、公認心理師のNicoです。
Nicoの心理療法の庭へようこそ。

今回は、障害年金申請の書類の書き方についてのお話です。
これを読めば、書類作成が楽になるはず!
前回の記事#11では、障害年金の概要と申請手続きの流れについて解説しました。
申請において特に重要な書類が、「病歴・就労状況等申立書」と、医師が用意する「診断書」でした。
- 「病歴・就労状況等申立書」は、発症前後の状況や治療の経過、現在の病状、生活や就労の状況を患者(もしくはその支援者)が整理し、障害年金の審査を行う認定医に伝えるものです。
- 「診断書」は、医師が患者のこれまでの治療経過と「病歴・就労状況等申立書」をもとに、「障害状態要件」を診断し、精神障害の程度(重症の度合い)を記載するものです。
前者は、基本的に患者が自分で書くもの(代筆は可)で、後者は医師が書く公的な書類です。
ただ、診断書に書いてもらう内容に関しては、患者側で「日常生活能力の判定項目」等についての「参考資料」を作成できれば、より正確な病状や生活状況を伝えられる診断書を作ってもらえるでしょう。
ただし、この参考資料は、必須はないので、「もし余力があれば」程度に捉えて下さい。
障害年金はそれなりの金額が支給されるため、その申請には、時間と労力がかかります。
重たい症状があるなかで、これらの手続きは大きな負担となるでしょう。
そのため、障害年金の申請手続きを代行する仕事をする専門家もいるくらいです。
申請代行を依頼する価値はあると思いますが、一方で「少しでも経済的負担を増やしたくない」という方もおられると思います。
そこで今回は、読者の方が自力で「病歴・就労状況等申立書」と診断書のための「参考資料」を少しでも楽に作成できるように、書き方のポイントを解説します。

以下の記述では、いくつか具体例を挙げていますが、
いずれも創作した架空の内容です。
病歴・就労状況等申立書のポイント
「病歴・就労状況等申立書」には表面と裏面があります(様式は、日本年金機構HP)。

まずは、表面の記載事項から説明するね。
傷病名
ここには、医師が下した診断名を書きます。障害年金の申請について相談した時点で、主治医に聞いておきましょう。
もしくは、これまでに「自立支援医療(通院精神)#6」や「傷病手当金#7」「精神障害者保健福祉手帳#10」などの制度を利用した時の診断名と同じであれば、それでも良いでしょう。
発病日
ここには、症状が出てきた日にちを書きますが、正確に記憶もしくは、記録できている人は少ないと思います。
そのため、医師に初診時の記録を確認してもらい、そのときに「いつごろから症状が出始めたと報告していたか」を聞いて書いても良いかもしれません。
症状が出始めた時期を報告していなければ、初診日から遡って、「〇年△月ごろ」と書いても良いでしょう。
当然ですが、「病歴・就労状況等申立書」と「診断書」のあいだで記述内容を一致させておきましょう。
初診日
「初診日」の定義は、「その病気に関して、生涯で初めて受診した日」ですので、それを書きましょう。
何度か転院を経験された人の場合は、「一つ目の病院を初めて受診した日」を書きます。
この初診日を証明するためにも、転院するときには、元の病院から紹介状(診療情報提供書)をもらって、病院を移ることが望ましいです。
もちろん、そうは言っても、医師との関係性によっては、紹介状をもらうのが難しい場合もあるかもしれません。
そのような場合に備えて、診察券やお薬手帳、領収証、診断書のコピー(取れた場合)などは、治療が修了するまでは保存しておくと役立ちます。
経過について
経過を書くための欄は、用紙1枚あたり5つあります。足りない場合には、2枚目を用意すれば問題ありません。
どの欄も、「期間」「受診の有無」「医療機関名」を左側に書き、右側には「その期間の状態と経過」について、『出来事』や『状態(とその変化)』などの事実を中心に書きます。
1つ目の欄には、「発病した時の状態と発病から初診までのあいだの状況」を書きます。
たとえば、次のように書きます。
〇〇年△月から☆☆年◇月まで 「受診していない」にチェック
〇〇年より5年間、事務職の正社員として、非常に忙しいながらも大きな問題なく就労していた。配置転換が行われた☆☆年△月から、業務量が激増し、ひと月当たりの残業が平均して100時間を超えるようになった。それが4か月続いたころから、思考力と集中力の低下、酷い倦怠感、頭痛、入床時の動悸、中途覚醒、早朝覚醒等が生じた。作業効率が落ちたことに加え、退職者が出たことからさらに業務量が増大し、仕事を持ち帰ったり、土日に出勤することも度々生じた。このころから、午前中特に強い倦怠感と抑うつ気分のために、布団から出るのにも長時間を要し、週に1,2回、以前にはなかった遅刻や欠勤をするようになった。
*ここでの書き方のポイントは、以下のとおりです。
- 大きな問題なく就労していた時期や期間から書く。
- 心身の調子を崩すきっかけになったと思われる「環境の変化」や「出来事」を書く。
- 心身に不調が出始めた時期と、継続した不調の内容を書く。
- 心身の不調による生活、学業、就労、対人関係上の支障や、できなくなったことを書く。
- 数字で示せる事柄は、なるべく明示して客観的に状態を伝えるようにする。
これによって、次のことが整理され、審査する認定医に伝わりやすくなります。
- 「発病する前から発病した時までの状態の変化」
- 「症状の程度と、それによる社会生活への影響の大きさ」

2つ目以降の経過を示す欄には、先の初診のあとに続く形で「3~5年程度の期間についての病状」を書いていきます。
治療期間がそれほど長くない場合には、症状や生活状況、就労状況などに何らかの変化があった時期を基準に区切ると、状況を整理して伝えられるでしょう。
この時期もたとえば、次のように書くことができます。
☆☆年◇月から☆☆+1年〇月まで(ここでは例として6か月くらいを想定)
上記の状態がさらに1か月続き、業務上の失敗も度々起こったために、上司より勧められて、同☆☆年◇月、~~~メンタルクリニックを受診した。食欲不振もあり体重が1か月で6㎏減少していた。中等症抑うつエピソードのために休職が必要と診断され、睡眠薬と抗うつ薬による治療を開始した。休職開始後は、午前中に離床し、日中をリビングでゴロゴロと過ごし、23時には就床し、一定のリズムで生活している。頭痛や中途覚醒は改善したが、早朝覚醒や強い倦怠感、抑うつ気分は大きく変わらず、食欲のない状態が続いていた。実家を離れた単身生活のため、身の回りのことは自分で行う必要があるが、5分程度の外出でも酷く疲れるので買い物も困難で、食料品はネットショップを利用した宅配頼みであった。調子が良い時以外は、料理も難しく、パンや冷凍食品、インスタントものを利用することが多かった。何事も億劫であり、殆ど外出せずの生活であるため、洗濯や入浴も週に1回程度で、汗を流す程度だった。通院は2週間に1回。
☆☆+1年〇月から☆☆+1年〇+6月まで(初診から1年後までの6か月間を想定)
☆☆+1年〇+2か月頃から、早朝覚醒は改善。生活リズムも一定。米を炊いたり、火にかけるだけの調理のほか、夕方ごろになれば徒歩5分のスーパーに行き、予め決めた物を買うことはできるようになった。一時期8㎏ほど減っていた体重も徐々に増え、同年〇+4か月頃には3㎏回復。休職開始時と比べると、倦怠感や抑うつ気分は若干和らいだが、頭にもやがかかったような状態は続いており、2,3ページの読書も疲れる程度だった。日中はテレビや音楽を流しているが、集中力も続かず、内容には興味や関心も殆ど湧かなかった。洗濯や入浴は週に1,2回程度で、洗髪のみ行っていた。通院は2週間に1回。
☆☆+1年〇+6月から☆☆+2年〇月まで(初診から1年6か月後までの6か月間を想定)
☆☆+1年〇+7月頃からは、週に2,3回10分程度の散歩に出られるようになり、買い物も予め決めた物以外にも、大まかな予算を考慮して購入するようになった。☆☆+2年〇月現在は、簡単な食事を作ることはできるようになっている。洗濯や入浴は週に2,3回程度で、たまに身体も洗えるようになった。通院は2週間に1回で、投薬に変更はない。
また、☆☆+1年〇+10月頃からは、ふと何かに関心が向くことも出てきて、知人に誘われて外出することもあるが、電車に乗ると緊張感の高まりや動悸が出現し、ひどく疲れて、数日ぐったりする。思考力、集中力の回復は鈍く、本やパソコンを開いても内容が頭に入ってこない感覚は、現在に至るまで継続している。一日を通して、抑うつ感や無気力感、虚しい感覚も続いている。最近は、経済的余裕も減ってきていることから、焦りの気持ちが強くなってきている。
*ここでの書き方のポイントは、次の通りです。
- 受診した時期、病院名、診断名、治療の方針や内容を書く。
- 仕事や学校の状態(休職、休学、退職など)を書く。
- 治療期間中の症状で変わったこと、変わらないこと(良い方向も、悪い方向も)を書く。
- 起床から日中の過ごし方、就寝、睡眠状態といった生活リズムについて書く。
- 食事、調理、洗濯、入浴、買い物や金銭管理といった衣食住がどれくらいできているか書く。
- 通院の頻度。治療方針の変化(変わらない場合は、変わっていないこと)を書く。
これによって、次のことが整理され、審査する認定医が病状をイメージしやすくなります。
- 「初診時の医師の診断」
- 「治療の進み具合と障害の状態。日常、社会生活がどこまでできて、何ができない状態か」
治療期間が長く、記載することがらが多い場合も、2つ目の欄以降と同じ要領で書いていけば良いです(必要な方は、2枚目、3枚目を作成します)。

表面はこれでOK!
次は裏面の記載事項を説明するよ。
裏面の記載事項
表面では、就労や就学、日常生活に大きな支障がなかった時期、もしくはまだ病院にかかっていなかった時期から、初診、障害認定日、現在にいたるまでの状況について整理しながら、具体的に書いてきました。
裏面では、障害認定日頃と、現在(請求日頃)の就労状況と日常生活の状況について、やや統一的に把握するための個別の質問に答えていく形式で記入します。

「1.障害認定日頃の状況」
障害認定日つまり、「初診から1年6か月」頃の状況についてです。
就労状況に関しては、就労の有無により、記入事項が変わります。
就労していた場合は、
- 職種(仕事の内容)
- 通勤方法と片道の通勤時間
- 出勤日数(障害認定日の前月と前々月について)
- 仕事中や仕事が終わったときの身体の調子を簡単に記入。
→たとえば、『勤務中も全身の緊張感、息苦しさがあり、なんとか勤務を終えたあとは、ぐったりして何も手につかない状態だった』など。
就労していなかった場合(休職も含む)は、その理由をすべて選択します。
- 体力に自信がなかった
- 医師から働くことを止められていた
- 働く意欲がなかった
- 働きたかったが適切な職場がなかった
- その他(具体的理由を記入)
日常生活状況については、以下の項目について、4段階で回答します。
「1自発的にできた」
「2自発的にできたが援助が必要だった」
「3自発的にできないが援助があればできた」
「4できなかった」
- 着替え
- トイレ
- 食事
- 炊事
- 掃除
- 洗面
- 入浴
- 散歩
- 洗濯
- 買い物
さらに、その他日常生活で不便に感じたことがあれば、記入します。
「2.現在(請求日頃)の状況」
障害年金の申請をしようとしている現在の状況についてです。
こちらは、就労状況と日常生活状況、障害者手帳の3つについて記入します。
就労状況と日常生活の状況については、書く内容は「1.障害認定日頃の状況」と同じなので、それぞれについて現在の状況を書けば良いでしょう。
障害者手帳の交付を受けているか(持っているか)については、「1受けている」「2受けていない」「3申請中」のいずれかを選択します。
さらに、交付を受けている場合は、
- その手帳の種類(身体障害、精神障害、療育手帳、ほか)
- 交付年月日と等級
- 手帳に書かれている障害名
を記入します。
手帳を持っていない場合は、ここは空欄にしておきます。
以上が申し立て内容に関する記述です。
あとは、この書類を誰か他の人に書いてもらった場合には、代筆者の氏名と請求者本人からみた続柄(関係)を書きます。
最後に、請求者本人の住所、氏名、電話番号を書いて、病歴・就労状況等申立書は完成です。

お疲れさまでした。
「病歴・就労状況等申立書」の作成だけでも大変だったと思います。
ですので、ここから先は余力のある人向けです。
診断書のための「参考資料」の作り方
診断書を作成するときには、医師がこれまでの診察記録をもとに、必要事項を記入していきます。
ただ、診察のなかでそれらの記載事項すべてを伝えられているとは限りません。
特に、次の記載事項のなかには、診察で話題になっていないものが含まれやすいです(番号は診断書様式上の数字です。診断書の様式は、日本年金機構HP)。
⑦発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間についての陳述
⑨これまでの発育・養育歴、教育歴、職歴、治療歴
⑩日常生活状況、日常生活の能力の判定、程度、現症時の就労状況
もちろん、診断書を依頼したあと、診察の中で主治医と打合せをして、これらの内容を埋めていくこともあるでしょうが、受け取りまでに時間がかかってしまうかもしれません。
そこで、余力があるならば、上記のことがらについて「参考資料」を作成し、「病歴・就労状況等申立書」とあわせて、診断書を依頼するときに、主治医に渡すことを検討してみても良いでしょう。
これによって、必要なことがらをほとんど網羅した状態で診断書を書き始められるので、より早く受け取ることができるでしょうし、病状をより正確に伝えられる診断書を書いてもらえると思います。

⑦発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間についての陳述
これらの情報は、初診時に詳しく報告していることも多いでしょう。
一方で、後から思い出したことや、初診時には伝えられていなかったことも合わせて診断書に書いて欲しい場合には、参考情報として伝えましょう。
以下のことを目安にすると、書きやすいと思います。
初診までの情報として
- 発病に至る経緯、ストレス要因、症状が出始めた時期と、その時の症状
- 通院開始時期やきっかけ
- そのときの診断や治療方針、就労や就学、生活の方針(休職、入院、自宅療養など)
初診からの情報として
- その後、症状が改善・悪化・不変か(変化した時期も)
- 障害認定日もしくは申請日ごろも残っている症状、就労・就学・生活状況など、障害年金を受ける状態にあることを伝える内容。
たとえば、次のように書けるでしょう。
〇〇年△月ごろより、入眠困難と早朝覚醒、強い抑うつ感と倦怠感、易疲労感(注:ちょっとした活動でひどく疲れること)、動悸や頭痛があった。〇〇年▢月に職場の上司に勧められ、通院を開始し、同時に休職。~~(薬の名前)の処方により、入眠困難はやや改善した。しかし、抗うつ薬を増量して数か月経っても抑うつ感は軽快せず。数種類の抗うつ薬を試し、☆☆(薬の名前)に変更後1か月したころから、徐々に抑うつ感の改善が見られ始めた。しかし、◇◇年〇月現在に至るまで、易疲労性をはじめとして、電車に乗ったときの動悸や緊張感などの身体の症状は変わらず、通勤や継続的な作業は難しい状態が続いている。
なお、「陳述者の氏名」は、この情報を報告した人の名前を書きます。申請者本人やその親族、知人であることが多いと思います。
「請求人との続柄」は、情報を報告した人と、年金申請者の関係を書きます(配偶者、きょうだい、母、父、被依頼人など)。
「聴取年月日」は、情報を報告した年月日を書きます。

⑨これまでの発育・養育歴、教育歴、職歴、治療歴
「ア 発育・養育歴」には、出生時や幼少期に、現在の症状に関連すると思われる特徴的なことがなければ、「特記なし」で構いません。
何らかの発達障害で年金申請を行う場合には、たとえば「3歳児健診でコミュニケーションの発達の遅れの指摘を受けた」「初語が通常よりもかなり遅かったこと」「周囲の働きかけへの反応が極端に薄かったこと」などの情報を簡潔に書きます。
「イ 教育歴」には、幼児期からの就学状況について、「普通学級」「特別支援学級」「特別支援学校」などのチェックがあります。
「ウ 職歴」には、職歴がない場合は「なし」、ある場合は、職種や雇用形態、勤務形態などを簡単に書きます。内容を絞る必要があるときには、発病したころの仕事や最も長かった仕事について書くと、元気だったころの状態を伝える手がかりになるでしょう。
「エ 受診歴」には、今回申請する傷病に関連して受診した医療機関について書きます。
左から順番に、
- 医療機関名
- かかった期間(分かる範囲で)
- 入院か外来か
- そのとき伝えられた診断名
- 主な治療(薬物療法か精神療法が多いでしょう)
- 症状が軽快・悪化・不変のいずれか
を書くことになっているので、参考資料もその形式で作りましょう。
⑩(裏面)日常生活状況、日常生活の能力の判定、程度、現症時の就労状況
「ア 現在の病状又は状態像」「イ アについての程度・症状・処方等」は、主治医でなければ書けないでしょうから、参考情報として書くべきことはありません。
「ウ 日常生活状況」については、参考情報としてまとめられると思います。
- (ア)は、現在の生活環境と同居者の有無
- (イ)は、対人関係を含めた全般的な家庭、社会生活状況を具体的に記入します。
たとえば、「同居者以外との対人関係はほとんどない/15分程度の会話でもひどく疲れる」といった具合です。
「2日常生活能力の判定」 については、但し書きにもあるように「単身で生活するとしたら可能かどうか」が大切です。
それぞれの項目に関する申請者の日常生活能力について参考となる情報をまとめましょう。
そのとき、該当する能力が次の4段階のどの程度が主治医に伝わるように書きます。
- 一人でほぼ問題なくできる
- 一人でだいたいできるが、時には助言や指導が必要
- 助言や指導があれば、一人でもできる
- 助言や指導をしても、一人ではできない、あるいは行わない
| 日常生活能力 | 参考情報として盛り込む内容(具体的に書く) |
| (1)適切な食事 | 準備も含めて適量をバランスよく摂れるなど(朝、昼、晩の3食摂るか。自炊、レトルトなど)。 |
| (2)身辺の清潔保持 | 洗面、洗髪、入浴、着替え、自室の清掃や片付けができるなど(毎日、週1など)。 |
| (3)金銭管理と買い物 | 独力でお金の管理、やりくりができる。一人での買い物、計画的な買い物ができるなど(事前に決めた物なら買える、出先で考えながら買い物ができるなど)。 |
| (4)通院と服薬 | 規則的に通院、服薬すること、病状や生活状況を主治医に伝えられるなど(決められた用法用量を守れる、重要なことは相談できるなど)。 |
| (5)他人との意思伝達及び対人関係 | 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動ができるなど(家族相手ならば可、職場の人が相手では無理など)。 |
| (6)身辺の安全保持及び危機対応 | 事故等の危険から身を守る能力がある、いつもと違うことが起きたとき、他人に助けを求めるなどして、適切に対応できるなど(動きが遅く、ぼんやりしているので危ないと指摘されるなど)。 |
| (7)社会性 | 銀行でのお金の出し入れ、公共施設の利用が一人でできる。社会生活に必要な手続きが行えるなど(書類に自分の住所を書くことすらままならないなど)。 |
「3 日常生活能力の程度」 については、状態をもっとも適切に説明できる障害として、「精神障害」もしくは「知的障害」のどちらかを選択し、該当すると主治医が判断したものを1つ選択する形式になっています。
先にまとめた「 2 日常生活能力の判定」の参考情報があれば、十分と思います。
「エ 現症時の就労状況」については、現在の仕事、発病前後の仕事、あるいは発病よりも前の仕事について、以下の事柄がわかる参考情報をまとめます。
- 一般企業/就労支援施設/その他(具体的に)
- 障碍者雇用/一般雇用/自営/その他(具体的に)
- 勤続年数
- 仕事の頻度(週または月に何日程度か)
- ひと月の給与のだいたいの金額
- 仕事内容
- 仕事場での援助の状況や意志疎通の状況 例:常に助けが必要/支障はなかった
「キ 福祉サービスの利用状況」については、利用している福祉サービスがあれば記入し、なければ「なし」で良いでしょう。
以上で、患者側でまとめることができる参考情報はほぼ揃うはずです。
さらに情報が必要になったときには、主治医から聞かれるので心配不要です。

診断書をもらったときに、驚かなくて良いように一言。
「⑫予後」については、「予後不良」「改善の見込みなし」「不詳」などと記載されることがよくあります。
このような記述を目にした患者さんの中には、落ち込んでしまう方もいるかもしれません。
しかし実際には、「明らかに良くなる見込みがあるならば、障害状態とは見なされにくい」と考えられることから、こうした記述はむしろ自然なことなのです。
あくまで診断書は、事務上としての判断のために作成するものなので、なるべく明快で簡潔であることが求められるのだ、と割り切ってかまいません。

障害年金の申請は、作成する書類が多いですが、受給できればメリットも大きいです。
今回の記事によって、自力での書類作成が少しでも楽になれば幸いです。
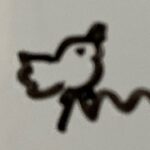
今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。
- 臨床精神医学編集委員会(編集)(2023)精神科診療に必要な書式マニュアル[第五版].臨床精神医学 第52巻増刊号(2023).アークメディア.
Nico
30代の臨床心理士、公認心理師。教育機関や精神科クリニックで、心理療法(カウンセリング)や心理検査を行ってきました。利用者にとっても、提供者にとっても、より良い臨床心理援助の形を創っていくことに関心をもって活動しています。
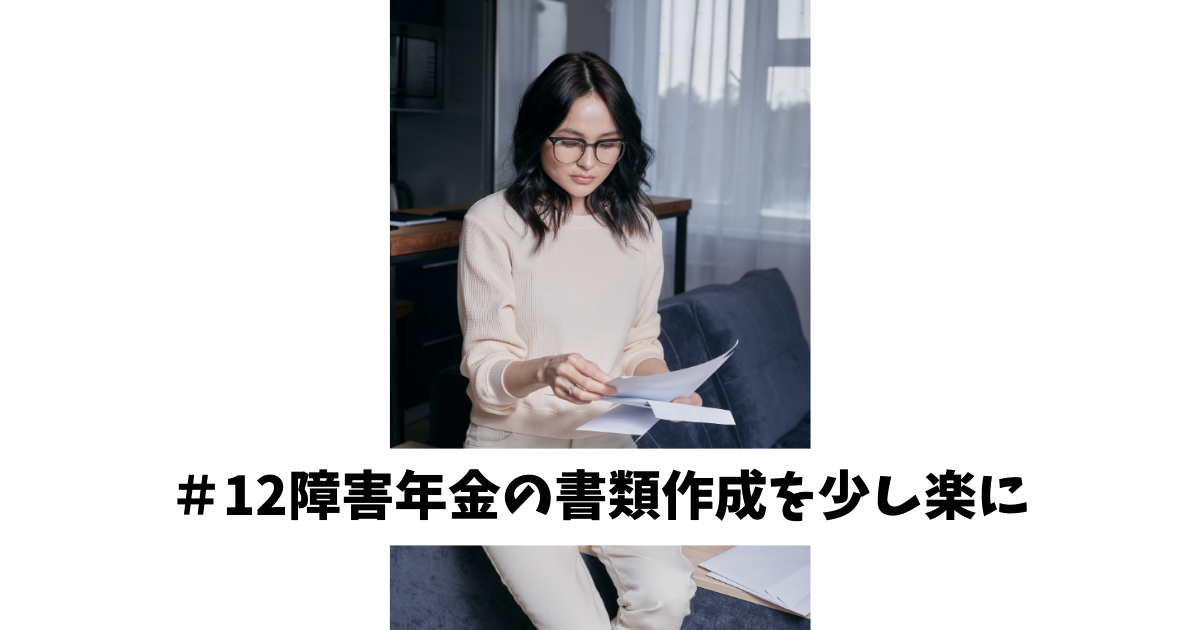

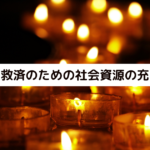
コメント