
皆さん、こんにちは。臨床心理士、公認心理師のNicoです。
Nicoの心理療法の庭へようこそ。

今回は、精神保健福祉手帳(いわゆる精神障害者手帳)についてのお話です。
精神疾患にかかると、満足に働けなくなって収入が大幅に減ってしまったり、通院費、治療費がかさんでしまったりして、経済的に苦しくなることが多いです。
精神疾患のために、ただでさえしんどいところに、経済的問題が重なると、安心して治療や休養に専念することが難しくなりかねません。
そこで、このブログでは、経済的負担を軽減するために利用できる公的な制度について解説しています。
精神障害者保健福祉手帳は、障害者の自立と社会参加の促進を目的とした制度です。申請により、一定の精神障害の状態にあると認定を受けることで、さまざまな支援を利用できるようになります。
この制度自体については、厚生労働省やお住いの自治体のHPでも調べることができますが、ここでは、私が申請に携わった経験をもとに、具体的な手続きと注意点、その対策と併せて、次のように3つに分けてお伝えします。
1.手帳を取得することで利用できる支援(メリット)
2.デメリットは特にない
3.手帳取得に必要な手続き6ステップと注意点、その対策
それでは、順番に見ていきましょう。
1.手帳取得により利用できる支援(メリット)
利用できる支援は、全国一律の支援と自治体独自の支援があり、手帳の等級によっても変わってきます。
1-1 支援内容
ここでは、経済的メリットの大きい代表的なものをいくつか紹介します。より詳しくは、自治体HPや自治体の担当窓口で配られるパンフレットなどで確認出来ます。
- NHK受信料の減免
- 所得税、住民税の控除
- 相続税の控除
- 自動車税、自動車取得税の軽減(1級のみ)
- その他、障害の程度、年齢、所得状況、扶養状況に応じた手当の給付、貸付
このなかでも、所得税、住民税の控除は、もっとも利用しやすく、経済的メリットが大きいでしょう。確定申告の際に、障害者控除を選択することで利用できますし、各税金担当窓口でも手続きできます。
- 鉄道、バス、タクシーの運賃の減免
- 上下水道利用料金の割引
- 携帯電話料金の割引
- 公共施設利用料の減免
他にも自治体ごとに、さまざまなサービスが行われていますので、お住いの自治体やご利用のサービス運営者に問い合わせて確認してみるのも良いと思います。
1-2手帳の障害等級について
障害等級の基準は、以下のようになっております。
| 1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
この等級の判定は、医師の診断書をもとに行われます。
そのため、普段の診察から、ご自身の生活状況(精神症状に加えて、対人関係、仕事、衣食住などの活動も含む)を医師に伝え、コミュニケーションを取っておくことが大切です。
2.デメリットは特にない
精神障害者保健福祉手帳の取得には、たしかに手続きの手間や労力はかかります。しかし、手帳を持つことによるデメリットは特にありません。
とは言え、次のような心配が浮かんでくることも自然かと思います。
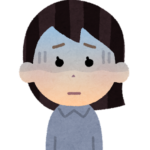
「一度障害者手帳を取得すると、ずっと障害者になる?」

手帳は2年ごとの更新制で、障害が軽くなれば、手帳の返納や、更新しないという選択もできますよ。
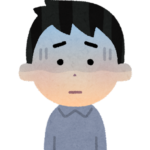
「手帳を取得すると障害があることが知られて、不利益を被るのでは?」

この制度にもとづく支援や配慮を受けたい場合にだけ、手帳をもっていることを伝えればよいので、それ以外の場合、知られたくない相手には伝える必要もありません。
つまり、手帳は、障害の程度に応じた支援を受ける権利を示す手段であって、その権利を使うかどうかは、その都度、選択することができるわけです。
デメリットは特にないうえ、上記以外にもさまざまなサービスが利用できますので、積極的に利用して、少しでも生活を楽にしましょう。
3.手帳取得に必要な手続き6ステップと注意点、その対策
ステップ1.申請する資格要件と必要書類の確認
まず、手帳を申請するためには、何らかの精神障害により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があり、該当する精神障害の初診日から6か月以上経っていることが必要です。
精神障害の例をあげると、次のようなものがあります(全ての精神障害が対象)。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
なお、知的障害については、療育手帳という別の制度の対象となっています。精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の両方を利用することも可能です。
次に、申請に必要な書類4点を確認します。
- 申請書
- 診断書または、精神障害による障害年金を既に受給している場合は、障害年金受給の証書等の写し
- 手帳に貼る証明写真
- 本人確認のための身分証明書(マイナンバーカードなど)
2に関しては、精神障害者保健福祉手帳は初診日から6か月経過すれば申請可能であるのに対して、障害年金は初診日から1年6か月経過していることが必要です。そのため、初めての申請では多くの場合、次に説明する診断書の提出による申請になるかと思います。
ステップ2.主治医への相談、診断書作成依頼
申請要件を満たしていることを確認できたら、手帳を取得したいという希望を主治医に相談し、診断書の作成を依頼しましょう。この診断書は、実費負担です。
診断書はお住いの自治体ごとに様式が指定されていますので、その様式は、こちらが用意するのが良いか、主治医が用意してくれるか尋ねましょう。
こちらが用意する場合は、次のどの形式がよいか確認しておきましょう。
①印刷された紙媒体(手書き)
②PDFファイル(手書き)
③Wordファイル(PCで入力)
主治医が指定様式の用意をしてくれる場合は、念のため、お住いの自治体を伝えておきましょう。
*自治体指定の様式と違うなどの不備があると、修正、再提出の手続きが必要になります。申請結果が出るまでの時間が延びてしまいますので、注意しましょう。
ステップ3.各自治体指定の診断書・申請書の様式の用意
こちらが様式を用意する場合、診断書、申請書の様式は、お住いの自治体のHPでダウンロードまたは、窓口で入手できます。
様式を入手したら、主治医に渡し、診断書を書いてもらい、4.申請手続きに移ります。
ここで注意点です。
多くの場合、診断書を作成するには、初診時からの申請までのカルテを調べて、様式に合わせて整理する時間が必要です。そのため、病院が混んでいて、十分に時間が取れない場合などは、診断書の受け取りが後日になることもあります。
また、ヒューマンエラーは望ましくはないのですが、主治医や病院が忙しくて診断書の作成を忘れられてしまうケースもあります。特に、書類が返送された場合、他の書類の山に埋もれてしまうことがあり得ます。
これらに備えて患者の側でできることとしては、次のようなことがあるでしょう。
①なるべく早い時期に主治医への相談、申請手続きにとりかかる(これが一番大切です)。
②「確定申告などで障害者控除を利用するために、早めに手帳取得したい」と急いでいることを主治医に伝える。
③申請書類を提出したあとは、そのことを主治医に報告し、もし書類が病院に返送されて来たら教えてほしいと伝える。
④病院に返送された場合、再提出の見通しを教えてもらう。
⑤その後、再提出がどうなったか聞いてみる。
これらによって、手帳発行までの見通しが立ち、時間と気持の余裕も生まれやすくなるでしょう。
ステップ4.申請手続き
診断書も準備できたら、先に触れた必要書類4点をもって、自治体の担当窓口に行き、手続きをします。再確認しておきましょう。
- 申請書
- 診断書または、精神障害による障害年金を既に受給している場合は、障害年金受給の証書等の写し
- 手帳に貼る証明写真
- 本人確認のための身分証明書(マイナンバーカードなど)
そこで診断書と証明写真を提出し、必要書類に記載することで手続き完了です。
手続きに問題がなく、申請が認められれば、3か月ほどで手帳が発行されます。
ステップ5.発行された手帳を受け取りに行く
申請が認められると、通知書が送られてきます。
その通知書と身分証明書をもって、窓口に行き、手帳を受け取りに来たことを伝えます。
窓口職員と一緒にパンフレットなどを見ながら、 障害等級やそれに応じて利用できるサービス、更新手続きなどについての説明を受けます。わからないことがあれば、聞いておきましょう。
説明が終われば、手帳を受け取って、支援の利用開始です。
税金の控除の申請をしたり、さまざまなサービスを利用して、生活を楽にしましょう。
ステップ6.更新のタイミング
手帳の有効期限は、手帳に日付が書かれているのですぐわかりますが、制度としては、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
更新の手続きは、有効期限の3か月前からできます(自治体によって多少変わる可能性もあります)。その際にも、診断書または年金証書等の写しが必要です。
なお、障害が軽くなった場合には、手帳の返納や、更新しないという選択もできますので、タイミングが近づいたら、主治医と相談しましょう。
少しでも生活を楽にするために申請の検討を。
以上、今回は、精神障害者保健福祉手帳について、私が申請に携わった経験も踏まえて以下の3つに分けてお伝えしました。
1.手帳を取得することで利用できる支援(メリット)
- 全国一律のものと自治体独自のものがある
- 等級によっても利用できる支援が変わる
- 所得税や住民税の控除をはじめ、経済的負担を軽減できる支援が受けられる
2.手帳取得によるデメリットは特にない
- 必要なのは、手続きの労力と診断書代金くらい
- 手帳を利用して支援を受けるかは自分で決められる(障害を知らせなくても良い)
3.手帳取得に必要な手続き6ステップと注意点、その対策
- 資格要件と必要書類の確認
- 主治医への相談、診断書の依頼
- 指定様式の用意、診断書の受け取り
- 申請手続き
- 手帳の受け取り
- 更新
注意点としては、手続き上の不備やヒューマンエラーの可能性も踏まえておくことです。
不備や問題は望ましくないですが、患者側でも対策をしておくと、「治療の主体は自分である」という感覚を強めてくれます。この感覚は、回復プロセスでも、その後の人生でも支えとなる大切な感覚です。対策の基本方針は、次の3つにまとめられます。
①必要な支援を受けられる診断書を書いてもらうためにも、普段の診察のなかで、精神症状だけでなく、対人関係、仕事、生活状況などを主治医に伝えておく。
②主治医への相談は早めに始め、進み具合をときどき確認して気持の余裕を確保する。
③お住いの自治体指定の様式を使う。
治療、療養中の経済的負担を減らすために、制度の利用を検討するお役に立てれば幸いです。
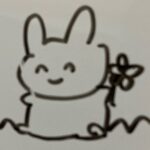
まずは制度や支援について知り、少しずつで良いので、自分に必要なものを選択してゆくことで、治療もはかどると思います。
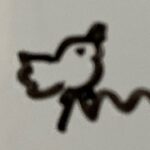
今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html 2023年2月27日最終閲覧.
Nico



コメント