
皆さん、こんにちは。臨床心理士、公認心理師のNicoです。
Nicoの心理療法の庭へようこそ。

今回は、障害年金についてのお話です。
盛りだくさんだけど、わかりやすく説明するよ。
前回まで、精神疾患のために働けなくなったとき、通院開始すぐから、1年半までのあいだに利用できる公的な経済支援制度を順番に解説してきました。
| 利用できる時期、条件 | 利用できる制度 | 手続きについて |
| 通院開始すぐに利用可能 | 自立支援医療(通院精神) | 専用の診断書が必要(自費) |
| 会社員等=健康保険加入者連続4日以上休職・通算1年半まで | 傷病手当金 | 専用の診断書が必要(保険適用) |
| 自営業者等で収入が大幅減 | 国民健康保険の保険料減免申請 | 自治体の窓口で手続き |
| 収入が大幅減 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請 | 年金事務所で手続き |
| 初診日から6か月以降 | 精神障害者保健福祉手帳(所得税・住民税等の控除) | 専用の診断書が必要(自費) |
今回は、精神疾患のために働けない期間が1年半以上になったときに利用できる障害年金制度について解説します。
障害年金は、患者も医師もともに、書類作成や手続きに時間と労力はかかりますが、申請が認められればメリットが大きい制度です。
この記事を読んで知識をつければ、手続きの労力が少し軽くなり、限られた診察時間のなかでも、より満足度の高い治療を進められると思います。
以下、順番に
- 障害年金制度の概要
- 「精神の障害」の申請区分に該当する疾患など
- 2種類の請求方法
- 手続きの流れ
- 申請手続きの注意点と、患者側でできる対策
- 精神疾患になったときへの備え
について、なるべく噛み砕いて説明していきます。

1.障害年金制度の概要
障害年金の種類と等級、保険料納付要件
障害年金制度は、大きく2つに分かれます。
| 障害基礎年金 | 原則、全員が対象 |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 厚生年金加入者のみ対象 |
障害年金を受給する要件は、申請する「精神の障害」に関して初めて病院にかかった日(初診日)が、どの時期にあるかによって2種類あります。
| 初診日が20歳より前にある場合 | ・障害の状態が等級要件を満たしていることが条件 |
| 初診日が20歳~65歳(公的年金加入中)の期間にある場合 | ・障害の状態が等級要件を満たしていることに加えて ・保険料の納付要件(後述)を満たしていることが条件 |
第1号被保険者が障害年金を申請する前に検討すべき注意点
国民年金第1号被保険者(自営業者など)が亡くなった場合には、その遺族には「遺族年金」「死亡一時金」もしくは「寡婦年金」のいずれかを選択して受け取る権利が発生します(その他の第2号、第3号被保険者の場合、「死亡一時金」「寡婦年金」はありません)。
しかし、第1号保険者が障害年金を受け取った場合、亡くなったとしても、遺族が「死亡一時金」や「寡婦年金」を受け取る権利が発生しなくなります(遺族年金については、このような除外基準は見当たりませんでした。間違っている場合は、ご教示ください)。
そのため、自営業者などの国民年金第1号被保険者の方が障害年金を申請する場合には、この点を一度検討しておく必要があるでしょう。

参考までに、
- 死亡一時金は、保険料を納めた月数に応じて、12万~32万円
- 寡婦年金の額は、第1号被保険者が保険者であった期間で計算した老齢年金の4分の3
となっているよ。
障害年金の受給額の方が多そうな場合や、療養生活をまずは優先した方が良い場合には、障害年金を申請する方が良いでしょう。

私としては、よほどのことがない限り、今の治療を乗り切り、生活を立て直すことを優先するのが良いのではないかと思います。

障害基礎年金
障害基礎年金は、「65歳になる前に初診日のある病気やけがで、障害の状態が障害等級表に定める1級または2級に該当しているとき」にもらえる年金です。
現在の制度では、20歳以上65歳未満の国民全員が、基礎年金に強制加入することになっているので、次に述べる保険料納付要件を満たしていれば、申請可能です(日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の受給要件)。
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の受給要件 太字はNico
注)国民年金の保険料を納めることが難しい場合は、絶対に未納にせず、窓口に相談して「保険料免除・納付猶予制度」を利用しましょう(参照 #9 国民年金保険料免除・納付猶予でお金の不安を軽減しよう)。
障害基礎年金の等級、基準となる障害の程度、受給金額については、次の表のとおりです。
| 等級 | 障害の程度 | 受給金額(年額) |
| 1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態 | 993,750円 |
| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害 | 795,000円 |
なお、受給者に18歳未満の子どもがいる場合は、人数に応じた加算があります(日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から))
1級は、炊事、洗濯、買い物、金銭の管理など、日常生活のほとんどに他者の助けが必要な場合を指すと考えられます。
2級は、簡単な食事を作ることは何とかできるものの、ひとりで買い物に行き、何を買うべきか考えるのは難しいなど、日常生活を満足に行うことが難しく、労働も困難な場合に認められます。

障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、「厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで、障害の状態が障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当しているとき」に、障害基礎年金に上乗せでもらえる年金です。
厚生年金には、サラリーマンや公務員など、「雇われて働いている人」が加入します。
厚生年金への加入条件は、法改正により、拡大してきているため、厚生年金に加入できる人の数は以前よりも増えています。
参考として、令和4年(2022年)10月から厚生年金(社会保険)の加入対象になる条件をあげておきます。
以下のすべてを満たす人が加入対象に追加されています。
- 従業員数101人以上の企業で働いていること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く人と同じ)
- 学生ではないこと
また、障害厚生年金を受給するためには、障害基礎年金のときと同様の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
会社などに勤め、厚生年金保険に加入している方は、国民年金や厚生年金の保険料の支払いは、給与から天引きの形で会社が行っています(保険料の半分は会社が負担)。
そのため、お勤め期間中の保険料については、ご自身で支払い手続きする必要はありません。
注意すべきは、退職などにより、ご自身で国民年金保険料の支払い手続きをする必要があった期間です。
ここで未納が多いと、障害年金が受給できなくなる場合があります。

先にも触れましたが、保険料納付が難しい場合は、「保険料免除・納付猶予制度」を使いましょう(参照 #9 国民年金保険料免除・納付猶予でお金の不安を軽減しよう)。
なお、障害基礎年金と違う点として、障害厚生年金では、1級、2級に加えて、3級があります。
1級、2級は、障害基礎年金と同じ基準です。3級は、日常生活はほぼ問題なく送れるものの、労働時間や形態は大きく制限される場合に認められます。
そのため、障害基礎年金は受給できなくても、3級の障害厚生年金をもらえることがあります。
また、障害基礎年金は、等級によって受給金額が一律で決まっていますが、障害厚生年金は、障害の等級と、その人の給料をもとに計算されるため、人によって受給金額が変わります。
ここでは、制度を大まかに理解することが目的なので、障害厚生年金の年金額の算出方法は扱いません。詳細を知りたい方は、国民年金機構HPを参照してください(「障害厚生委年金の受給要件・請求時期・年金額」「報酬比例部分」)。
障害厚生年金の等級、基準となる程度をまとめると、以下の表のとおりです。
| 等級 | 障害の程度 |
| 1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態 |
| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方 |
また、厚生年金加入者で、「初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったとき」には、「障害手当金(一時金)」が支給されます。
障害手当金の金額は、毎年算定し直されることになっています。

ここまでを簡単にまとめるね。
- 障害の程度が重い順に1級、2級、3級(3級は障害厚生年金のみ)がある。
- 年金保険料を3分の2以上の期間納めていれば、誰でも障害基礎年金を申請できる。
- お勤めの条件により厚生年金に加入していれば、障害厚生年金もプラスされる。

障害基礎年金だけを受けられる方も、障害厚生年金もあわせて受けられる方も、これ以降の請求、申請の方法は、「年金請求書」の様式が異なる以外は同じです。
2.「精神の障害」の申請区分に該当する疾患など
現在用いられている障害認定基準によると、「精神の障害」の申請区分に該当する精神疾患や障害は、次のようになっています(日本年金機構HP 国民年金・厚生年金 障害認定基準 第3 障害認定にあたっての基準 第1章障害等級認定基準 第8節 精神の障害)。
| A.統合失調症、統合失調型障害、妄想性障害、気分(感情障害)障害 | ・統合失調症など。 ・気分(感情)障害:うつ病、双極性障害など。 |
| B.症状性を含む器質性精神障害 | ・先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経系の器質障害を原因として生じる精神障害(高次脳機能障害を含む)。 ・膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害。 ・アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神および行動の障害(精神病性障害や明らかな身体依存が見られるもの)。覚せい剤中毒などの故意の犯罪行為に該当するものは対象外。 |
| C.てんかん | |
| D.知的障害 | |
| E.発達障害 | ・自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害 ・学習障害 ・注意欠陥多動性障害など |

なお、「人格障害」や「神経症(摂食障害、依存症、不安神経症、強迫神経症など)」は、原則として認定の対象となりません。

ただし、「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱う」という例外規定も存在するよ。
3.2種類の請求方法
障害年金の請求方法は、「いつごろ年金受給条件に該当する障害状態になったのか」という時期に応じて、障害認定日による請求と事後重症による請求の2種類があります。
初診日から1年6か月を過ぎた日を「障害認定日」と言い、この日に障害等級の条件(障害状態要件)を満たしているとき、「障害認定日による請求」ができます。
この場合、障害認定日から3か月(初診日から1年9か月)以内の状態についての診断書を用いて障害年金の受給申請を行うことになります(初診日が20歳よりも前にある場合は、障害認定日の前後3か月の状態についての診断書)。
この方法による請求は、障害認定日以降であれば、いつでも可能ですが、受給できる障害年金は、申請した時点からさかのぼって5年分が限度になっています。
また、障害認定日と申請時点が1年以上離れている場合、2通の診断書提出を求められるようです。そのため、「障害状態要件」を満たしたら、なるべく早めに申請手続きをする方がよいでしょう。
上記の障害認定日の時点で、「障害状態要件」を満たしていなかったとしても、その後症状が悪化して、条件を満たすようになったときには、「事後重症による請求」ができます。
ただし、請求書の提出は、65歳の誕生日の前々月までに提出する必要があります。
また、事後重症による請求の場合、請求した日の翌月分から障害年金を受け取ることになりますので、やはり早めの申請手続きが望ましいです。
なお、障害認定日による請求を行ったものの、認められなかったという場合でも、事後重症による請求は何度でも行うことができます。
そのため、過去に申請が認められなかったとしても、症状が悪化して就労や生活に大きな支障が出るようになったのであれば、再度申請することを検討しても良いでしょう。
4.手続きの流れ
障害年金を申請しようと決めてから、受給するまでの大まかな流れは、次のようになっています。
- 年金保険料の納付要件を満たしているか確認し、主治医に申請したい旨を相談する。
- 年金事務所で自分の申請について確認し、制度説明を受け、申請に必要な書類をもらう。
- 患者側で用意することになっている書類を書く。
- 主治医に診断書を書いてほしい旨を伝え、必要書類を渡し、後日、診断書を受け取る。
- 必要書類を揃えて、年金事務所に提出する。
- 申請結果が届くのをゆっくり待つ(約3か月。入金はさらに1,2か月先。2か月に1回、2か月分がまとめて振り込まれる)。
順番に見ていきましょう。

1.納付要件の確認と主治医への相談
保険料の納付要件については、制度概要のところで説明しました。
次に、申請に動く前に、予め主治医に相談し、現在のご自身の病状が「障害状態要件」を満たしていそうか(等級に該当しそうか)を確認しておきましょう。
障害年金の申請に限らず、より良い治療を進めるにあたって重要なことは、「重要な決断、行動をする前に、まずは相談すること」です。
「自分のことは自分が一番わかっている」というのは、ひとつ確かなことです。
その一方で、「自分では見えていない部分があって、ときにはそれが大事なポイントだった」ということも、案外よくあるものです。
この「重要だけれど、自分では見えていない部分」がないかを知る上で、他者(この場合は主治医)に相談することは非常に重要です。
特に、診察での情報を元に診断を行い、障害状態要件を満たしているか判断するのは、医師だけに許された仕事ですので、その判断を先に聞いておくことは重要です。

自分では要件を満たしていると思って申請書類を作成しても、主治医が障害状態要件を満たしていないと判断すれば、それまでの労力が無駄になってしまうからね。
2.年金事務所での自分の申請について確認~書類をもらう
このステップは必ず踏んでください。なぜなら、個人の受診歴や就労歴、保険料の納付状況によって、必要な書類が異なる場合があるためです。
このステップを飛ばして、書類を準備すると、必要な書類が不足して、さらに手間がかかり、申請が遅れるなどのトラブルが起こりかねません。
そのため、面倒でも一度窓口に出向いて、「自分の場合は、どの書類が必要か」必ず、一緒に確認してもらいましょう。

具体的にはまず、日本年金機構HPから、最寄りの年金窓口を調べます(全国の相談・手続き窓口)。つぎに、「予約受付専用電話」に電話をかけて、手続きのための日時を予約をします(日本年金機構HP 予約相談について)。
この予約電話の際に話した内容をもとに、窓口スタッフが必要書類を予め用意してくれるので、当日の話し合いがスムーズに行えます(日本年金機構 予約相談について)。
予約の日時が来たら、用意するように求められた書類などを持って、最寄りの年金窓口に行って相談をします。予約をしているので、待ち時間もほぼゼロのはずです。
自分の番が来たら、窓口スタッフの方が事前の準備にしたがって、保険料納付の状況や申請できる年金の種類、これから用意する必要のある書類などを一緒に確認してくれます。

必要書類一覧にチェックを入れながら説明してくれますが、情報量が多いので、心配な方は、一緒に説明を聞いてくれる人についてきてもらいましょう。
3.患者側で用意する書類について
障害年金申請にあたって、全員必須の書類は以下の6つです。このうち①と②は患者側で作成する必要があります(障害基礎年金のみの場合と、障害厚生年金も申請する場合とで、①の様式は異なる)。
| ①年金請求書(基礎年金のみの様式/基礎・厚生両方の様式) | 患者が作成 |
| ②病歴・就労状況等申立書 | 患者が作成医師が診断書を作成するときの参考にもなる |
| ③専用の様式の診断書 | 医師が作成(次の項で説明) |
| ④受取先金融機関の通帳等 | 本人名義 |
| ⑤本人の生年月日を明らかにできる書類 | 住民票やマイナンバーカードなど |
| ⑥基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | 年金手帳など |
①~③の様式は、日本年金機構のホームページでもダウンロードできます
①は手書きせざるを得ませんが、②と③はエクセルファイルをダウンロードすれば、PCで作成できます。
以上の6つの書類に加えて、「はじめてかかった医療機関(初診日)と診断書を作成した医療機関(現在)が異なる場合」には、⑦受診状況等証明書(初診日の確認が目的)が必要になります。
ただ、次のような場合には、この書類を用意することが難しいかもしれません。
- 初診を受けた病院が閉院した場合
- 転院して時間が経っているため、前の病院のカルテが破棄されていた場合
- 前の主治医に伝えることなく転院した場合(紹介状がない、前医との関係が悪い)

それでも、次のように、初診日を証明する手段がありますので、諦めないでください(日本年金機構 障害年金の初診日証明書類のご案内)。
| 20歳以降に初診日がある場合 | 第三者証明(2通)と参考資料を用意 |
| 初診日に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意 | |
| 20歳より前に初診日がある場合 | 2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を用意 |
| 第三者証明(2通)を用意 | |
| 初診日に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意 | |
| その他の証明方法*受診状況等証明書が添付できない申立書を使用 | 初診日が存在進期間を証明する参考資料を用意 |
| 初診日の記載された、請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテ等を用意する |
また、以下に当てはまる方などは、追加で必要な書類があります。
- 未成年の子どもがいる方(もしくは20歳未満で障害の状態にある子どもがいる方)
- 障害の原因が第三者の行為による方
- 共済組合に加入されていた期間がある方
- 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)

より詳しくは、日本年金機構HP「障害基礎年金を受けられるとき」を参照してね。
4.主治医に診断書の作成を依頼し、後日受け取る
「病歴・就労状況等申立書」が作成出来たら、「診断書の様式」とあわせて、主治医に渡し、診断書の作成を依頼します(診断書代金は自費ですので、病院にお問合わせください)。
診断書の作成には、初診日から障害認定日、あるいは事後重症での申請で参照する診察日までのカルテを調べて、経過や現状を拾い上げる必要があるので、時間がかかります。
また、主治医が書類を作成した後、改めて確認や打合せの作業が入ることもあります。
そのため、多くの場合、診断書の受け取りは、後日ということになります。

診断書の様式の裏面には、「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」等を評価する欄があります。
この評価は医師が行うのですが、そのための情報源は、主に診察内容です。
普段の診察で細かな生活状況を伝えていれば、評価もしやすいのですが、十分に共有できている人の方が少ないかと思います。
そこで、「余力があれば」ですが、これらの項目ごとに、診断書が書かれる日にちの周辺でのご自身の生活状況をまとめた資料を作って、主治医に渡すと、作成がスムーズに進むだけでなく、より正確に障害状態要件を満たしているかの判定が行われるようになるでしょう。
5.必要書類を年金事務所に提出。
診断書も手に入れたら、6つの書類(人によってはもう少しある)を揃えて、年金窓口に提出に行きます。このときも、事前に「予約相談窓口」から、来所時間の予約を行いましょう(あるいは、初回の相談の時点で、予約を取っているかもしれません)。
6.結果が届くのを待つ。

書類を提出したら、これまでの頑張りをねぎらって、結果をゆっくり待ちましょう。
書類提出時に案内されますが、審査には約3か月かかります。給付決定のお知らせが届いた後、入金はさらに1,2か月先になります。
つまり、書類提出時点から、入金まで4,5か月はかかります。書類や手続きに不足などがあれば、さらに後ろにずれ込みますので、申請は早めに動き、正確を期すために確認をしましょう(窓口で記載漏れがないかの確認はしてくれます)。
入金のタイミングは2か月に1回、偶数月に、2か月分がまとめて振り込まれます。
5.申請手続きの注意点と、患者側でできる対策
障害年金は、保険料と国庫負担の財源から、相当の金額が支払われるため、審査基準がそれなりに厳しくなっており、そのための書類準備も大変です。
その一方で、精神疾患で十分な所得が得られなくなった状態では、安心して治療に専念するためにも、なるべく早い段階でもらえるようになること、手続きを抜け漏れなく、スムーズに進められることが重要です。
以下に、申請手続きに関する注意点と、患者側でできる対策ポイントを3つお伝えします。
ポイント1:申請は早め早めに動く。見通しを作る。
ここまでに既に何度か触れてきましたが、障害年金の申請から受給決定、初回の入金までにはかなりの時間がかかります。
そのため、生活が苦しくなってから検討を始めるのではなく、精神疾患による休職が始まった段階から、「申請するかもしれない」という可能性を頭の片隅においておきましょう。
そして、初診日から1年6か月が近づいてきたら、納付要件の確認と主治医への相談に動き出すと良いでしょう。
このように、できる事柄から手を付け、見通しを作っておくこと自体が、療養期間中に湧きおこる不安や焦りに対して、「今は休んでいて大丈夫」「あと〇か月してから動けばOK」というふうに、気持を少し落ち着けるうえで役に立つと思います。

早めに動いておけば、書類の追加や修正が必要になったときにも、少し余裕をもって対応しやすくなります。
ポイント2:できる範囲で自分の病状を掴み、主治医に伝えておく。

一見、地味で当たり前と思われるかもしれませんが、治療において一番大切なことです。
精神疾患の治療は特に、「先生にお任せ」ではなく、患者と治療者が一緒になって、不安や抑うつ気分などの精神症状、それに伴う身体の症状のほか、社会生活や就労への影響などの状態を確認し、進めていきます。
悪くなっているときには何らかの修正や介入を行いますが、症状が緩やかに良くなっているときや、少なくとも悪くなっていないときには、治療方針を変更することなく、継続することが多いです。
大きく悪化したときのことは、多くのかたが主治医に相談するでしょうが、それ以外の普段の状態もつかまえて、なるべく丁寧に主治医に伝えるようにして欲しいと思います。
「先生も忙しそうだから」「こんなこと言っても仕方ないかな」「憂うつと伝えれば十分かな」など考えて、ついつい遠慮してしまうかもしれませんが、そういう所にこそ、病状を具体的にイメージとして捉える上で大事なことが潜んでいるものです。

実際、普段の生活状況について治療者と一緒に丁寧に追っていくなかで、患者さん自身が「あ、実は回復が進んでいたんだな」と気づくことが、よくあります。
これらの情報は、障害年金の診断書にある「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」を評価する項目を記載する上でも、とても大切になってきます。
ですので、普段の診察から、以下のことを意識してもらえると良いと思います。
- 普段の通院から、自分の状態を丁寧に伝える(食事、日中の過ごし方、入浴、排便の状態など)。
- 自分でも通院状況、病状を日記などで記録しておく。家族に手伝ってもらっても良い。
- 転院するときは、紹介状(診療情報提供書)をもらっておく。これにより、経過や治療内容が引き継がれるため、処方の見直しや、年金等の申請時に病状や経過の証明、書類の作成が楽になる。
ポイント3:書類の作成は、手伝ってもらう。
申請書類の中には、患者が書くことになっているものが複数ありました。
日本年金機構のHPには、書類の記入例や記載要領も示されていますが、精神疾患で障害年金を申請するほどの状態にあるならば、制度に詳しくないかぎり、本人が独力で書類を作成することは、非常に難しいでしょう。
特に、病歴・就労状況等申立書は、発病前後から順番に現在までの状況について整理し、就労や生活が困難であることが、書類を審査する第三者にも客観的にわかるようにまとめる必要があるので、大変だと思います。
このようなときは無理せず、周囲の元気な人に手伝ってもらうか、社会保険労務士や精神保健福祉士など、書類作成経験のある人に仕事として依頼することを検討しましょう。
精神疾患にかかる人の中には、人を頼ることが苦手な方や、自分は人に助けてもらう価値がないと感じている方もおられるかもしれません。
しかし、だからこそ、人に助けを求めること、人を頼ることを少しずつ練習してゆくことが、今後の生活を少し楽にするために役立つのです。
ですから、最初は難しいかもしれませんが、少しずつでいいですし、仕事として頼んでもいいので、周囲の人に手伝ってもらいましょう。

注意点としては、書類作成を仕事として引き受けている人の中には、ごく一部ですが、なんとしても申請を通そうとして、実際と異なる内容を診断書に書くよう、主治医に強引な要求をしてしまう人がいることです。
診断書は公的な文書なので、事実と異なる記載をすることは法律違反になります。
このような依頼の仕方をすると、その後の主治医との関係を悪くしてしまう恐れもあります。
主治医から「現時点では障害状態要件を満たしている診断書が書けない」と言われた場合には、残念ですが、一旦、他の方法を考えましょう。

もちろん、その後、症状が悪化したときは、事後重症による請求ができないか相談すると良いよ。
6.精神疾患になったときへの備えー知識と貯金
#6から#11まで6回にわたって、精神疾患で働けなくなったときに利用できる公的な支援制度について解説してきました。
これまでの6つの記事を全て読まれた方は、もうお気づきかもしれませんが、こうした制度についての知識を身に着けていると、実際に精神疾患になったときの経済面についての見通しが以前よりもはっきりしたのではないでしょうか。
制度を知れば、「万が一のときに向けて、今から自分で用意しておく方が良いもの」と「自分で用意しなくても、制度を利用すれば済むこと」が明確になります。
それにより、「自分で用意すべきもの」だけにエネルギーを注げば十分なので、今の生活も少し楽になりますし、将来の不安も小さくなるでしょう。

知識は最大の備えのひとつになります。「知は力」です。
「自分で用意すべきもの」「制度だけでは足りないもの」がどれくらいあるのかが明確になれば、できる範囲で今から対策していきましょう。
障害年金の申請は、初診日から1年6か月以上経てばできますが、実際に障害年金を受け取るまでには、さらに6か月近くかかります。
それまでのあいだの経済的な備えとしては「貯金」が望ましいでしょう。
なぜなら、多くの民間保険は、「精神疾患が原因で入院したこと」が支払い条件に含まれていたり、支払期間が短いなど、精神疾患に対する保証が十分ではないからです。

どれくらい貯金しておけばよいかは、個人の生活費によるのですが、ここでは2つの場合に分けて目安を挙げておきます。
傷病手当金の利用で通算1年6か月のあいだは、給料の3分の2ほどを受け取ることができることを思い出してください。
そうすると、最初の1年6か月は傷病手当金でまかなうことになります。
次に障害年金を申請して、最初に振り込まれるまで、最低でも6か月分の生活費が必要になります。
そのため、6か月分以上の生活費を貯金しておくことが望ましいでしょう。
傷病手当金が利用できないので、障害年金が振り込まれるまで、最低でも2年分の生活費を貯金しておくことが望ましいでしょう。
もちろん、その間、これまでに紹介した公的な制度も利用して、税金や保険料等の経済的負担を軽くする対応も行います。
貯金として備えておく金額の計算の仕方は次のようになります。
たとえば、ひと月の生活費が20万円ならば、
(1)の場合:20万/月 × 6か月 =120万円以上
(2)の場合:20万/月 × 12か月/年 × 2年 =480万円以上
を貯めておくと良いことになります。
実際には、これまでに解説した各種経済的支援を利用し、税金や保険料等の経済的負担を軽くすることで、もう少し余裕が出ると考えられます。それでも、「無収入でも2年間の生活は安泰である」という状況を作っておくと、万が一のときにも、気持ちに余裕をもって療養生活が送れるでしょう。
なお、貯金を用意する余裕もないうちに精神疾患で働けなくなり、これまで紹介した公的制度を全部使っても、お金が足りないという見通しが立った場合には、「生活保護制度」の利用を考えましょう。
生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利(生存権)と、国家が国民の生活を保障する義務を規程した日本国憲法第25条の理念に基づいて作られた制度ですので、困ったときには積極的に検討しましょう(厚生労働省 ナショナルミニマムに関する議論の参考資料 および 生活保護法第1条)。
安心して療養生活を送るために障害年金の申請を検討しよう

最後にまとめです。
- 精神疾患で病院をはじめて受診した日(初診日)から1年6か月経過した時点で、「障害状態要件」と「年金保険料の納付要件」を満たしていれば、障害年金の受給申請ができる。
- 原則全員が対象となる「障害基礎年金」と、サラリーマンなどの厚生年金加入者が対象となり、上乗せで支給される「障害厚生年金」(障害手当金)がある。
- 請求方法は、初診日から1年6か月~1年9か月の間の障害状態で申請する「認定日による請求」と、それ以降に症状が悪化した場合に申請する「事後重症による請求」がある。
- 請求の流れは、納付要件の確認→主治医に相談→窓口で相談→書類作成→診断書の依頼、受け取り→窓口へ提出→結果を待つ。
- 申請のポイントは、「早めに動く」「状態を丁寧に伝える」「無理せず人を頼る」。
- 公的な制度で補えない部分は、予め貯金で備えておくと安心。それでも困るときには、生活保護制度というセーフティネットもある。

今回はとてもボリュームが多かったですね。
ここまで読んでくださった方、お疲れさまでした。
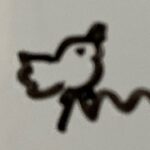
今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。
- 臨床精神医学編集委員会(編集)(2023)精神科診療に必要な書式マニュアル[第五版].臨床精神医学 第52巻増刊号(2023).アークメディア.
- 日本年金機構ホームページ 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(2023年5月15日閲覧)
- 日本年金機構ホームページ 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額(2023年5月15日閲覧)
- 日本年金機構ホームページ 遺族年金(2023年5月15日閲覧)
- 日本年金機構ホームページ 寡婦年金(2023年5月15日閲覧)
- 日本年金機構ホームページ 死亡一時金(2023年5月15日閲覧)
- 政府広報オンライン パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入により手厚い保証が受けられます(2023年5月15日閲覧)
- 政府広報オンライン 障害年金の制度をご存じですか?(2015年5月15日閲覧)
Nico



コメント