
皆さん、こんにちは。臨床心理士、公認心理師のNicoです。
Nicoの心理療法の庭へようこそ。

今日も一緒に心理学や心理療法について勉強しよう!
今日のテーマは、「心理療法(カウンセリング/セラピー)って何をするの?」です。
日本では、心理療法はまだまだ馴染みが薄く、敷居が高く感じられていると思います。
それは例えば、次のような不安や疑問に由来しているのではないでしょうか?

心理療法やカウンセリングに興味はあるけど、何をするのか分からない。
心理療法がどんなものかイメージしづらく本当にお金を払う価値があるかも不安。
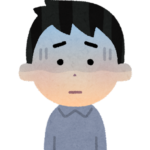
カウンセリングって話を聞くだけでしょ?それで本当に問題解決になるの?
他人に自分の悩みを話すのは恥ずかしい。責められるんじゃないか不安。

確かに、わからないと不安だね。

そうなんだ。わかると不安は小さくなるからね。
だから一緒に勉強して、知識を身に着けよう!
そこで今回は、心理療法について、次の3つの観点から解説します。
- 心理療法は何を目指しているのか。
- いろいろな学派・アプローチの共通点。
- 心理療法は結局、何をしているのか。
それらを知ることによって、
- 心理療法は自分にとって価値や意味がありそうか判断しやすくなる。
- 専門家にコンタクトを取り、一歩を踏み出すきっかけになるかもしれない。
- カウンセラー(セラピスト)の言動が、何を目指しているかわかりやすくなる。
と思います。

それでは、行ってみましょう!
心理療法の目指すところ
まず結論から言うと、
- 「心理療法は、来談者(クライエント)の心が生き生きすることを目指すもの」
と言って良いと思います。
日本心理研修センター(2018)によれば、心理療法には400以上の学派があり、それぞれが依って立つ思想や理論、価値観、方法論もさまざまです。
例えば、以下のような学派・アプローチがあります。
- 無意識の存在を仮定する深層心理学的アプローチ
- 症状を行動と認知で捉える認知行動療法
- 人間の本性は自己実現に向かうと考える人間性心理学派
- 援助対象をシステムだと考えるシステム論的アプローチ
- 多様な学派の視点や技法を生かそうとする統合的アプローチ
このように、心理療法にはさまざまな視点があります。
しかし、多くの研究により、学派間の治療効果の違いはわずかでしかないことも示されています(日本心理研修センター,2018)。
そのため、理論や方法論の違いはあれど、その目指すところは共通して、「悩みを抱えているクライエントが、より生き生きと生きられるように援助すること」にあるはずです。

代表的なアプローチの大まかな特徴と共通点
例えば、
- 深層心理学的アプローチでは、
無意識のままになっている感情や感覚を意識が体験し、自分のものとして生きられるようになることを目指します。
- 認知行動療法でも、
普段意識して振り返ることなく行っている認知や行動の偏りを点検し、よりバランスの取れた生き方ができるようになることを目指します。
- 人間性心理学派では、
人間の心に備わった「より良くなろうとする潜在的な可能性」が実現して、人格の変化を引き起こすことを目指します。
- システム論的アプローチは、
家族や職場など、個人が属するシステムが硬直してしまっている状態に介入し、システムと個人が柔軟性や新しい態度を獲得することを目指します。
より詳しい理論や方法は、今後少しずつ紹介していく予定ですが、今触れたところをまとめると、
- 心理療法では、クライエント個人(または周囲の環境も含めて)が、「まだ十分に生きられていない潜在的な可能性に触れ、新しい体験をしていくこと」を援助することが目標になっている
と言えるでしょう。

心理療法では何をするのか
多くの心理療法では、1回あたり45~60分程度の時間を取ります。
その中で、セラピスト(カウンセラー)は、クライエントが体験したことや感じていることをじっくりと聴き(訊き)ます。
クライエントのなかには、心理療法を始めるにあたって、
- 「ただ話をするだけで良くなるのか」
- 「話を聞いてもうらだけじゃなくて、具体的なアドバイスが欲しい」
と仰る方もおられます。
こうした疑問や希望は自然なことですし、心理療法では実際に具体的な提案をすることもあります。そしてその提案が有効な場合も沢山あります。
それに加えて、心理療法では、聴く/訊く(受け取る/尋ねる)ことをとても重視します。それは次の理由によります。
- 私たちは、自分が体験したことや感じていることを受け取ってくれる「他者」がいる状況ではじめて、それを言葉や形にする(語る/象る)ことができるようになる。
- その語りのプロセスのなかで、私たちは自分の体験、感じ方、考え方から少し距離をとり、対象として扱うことができるようになっていく。
- 自分の体験や自分が置かれている状況を徐々に俯瞰できるようになることで、自分に何ができるか、何が必要か、自分は何を大事にしたいのかを見つけやすくなる。
- 私たちは、他者の立場から言われたことよりも、自分自身で感じ、考え、発見したことの方が格段に納得しやすい(心理的変化)し、実行もしやすい(行動的変化)。
そのため、セラピストはまず、話を聴く/訊くことを通して、クライエントの潜在的な可能性や体験、クライエントの置かれた状況を仮説的に理解しようとします。
このときセラピストは、もっている知識と想像力、自らの感覚、感情などを総動員して、クライエントが上記のプロセスを進めやすくなるような問い(質問の仕方)を考えています。
こうして立てられた問いかけ(訊くこと)によって、クライエントが少し違った視点から改めて考えるきっかけを掴みやすくなることが狙いとなっています。
もちろん、すぐに望ましい問いが見つかるとは限りませんし、その問いを発するのを待つ方が良いときもあります。
クライエントが自ら語ることができるときや、たとえ声に出さなくてもクライエントが内側で想いを巡らしている様子のときは、セラピストはその心の作業を邪魔しないように聴きます。それによってセラピストの方も、クライエントへの理解や問いに一層磨きをかけていきます。
つまり、セラピストの聴く/訊く態度は、様々な要因によって身動きが取りにくくなっているクライエントの心が、生き生きと動けるようになるための環境・関係を目指していると考えられます。
私の考えでは、こうした心の作業プロセスが、本来の「共感」(empathy=感情や想像力を相手との関わりの中に差し入れる)であり、「傾聴」(active listening=心を能動的に働かせながら聴く/訊くこと)です。
心理療法は、このように、外からは「ただ聞いているだけ」にも見えるうえ、とても地道な心の作業の積み重ねを大切にしています。

「聞く」だけじゃなくて、いろいろ考えながら、積極的に質問もするんだね。

うんうん。だからよく、「一緒に考えよう」って提案するんだ。
まとめ 心理療法は何をするのか?
今回は、以下の内容をお伝えしました。
- 心理療法は、来談者(クライエント)の心が生き生きすることを目指すもの。
- セラピストは、聴く/訊く(受け取る/尋ねる)ことを通して、クライエントが自分の体験やものの見方を俯瞰し、自分にできること、必要なこと、自分がしたいことを発見し、行動に移してゆく心の作業を援助する。
- そのためにセラピストは、もっている知識と想像力、自らの感覚、感情などを総動員して、クライエントが心の作業を進めやすくなるような問い(質問の仕方)を考えながら聴いている。筆者の考えでは、ここに本来の「共感」「傾聴」がある。
- 心理療法では、このプロセスを「一緒に考える」と表現することがよくある。
こうした過程のなかで、症状や問題が消失したり、問題自体はなくならなくても、感じ方や向き合い方が大きく変化したりします。
これらは、実際に体験していただいて初めて分かってくるところが多いと思いますが、心理療法が提供する価値について少しでもイメージしていただければと思います。

文献
- 日本心理研修センター(2018)公認心理師現任者講習会テキスト 2018年版.金剛出版.
Nico


コメント